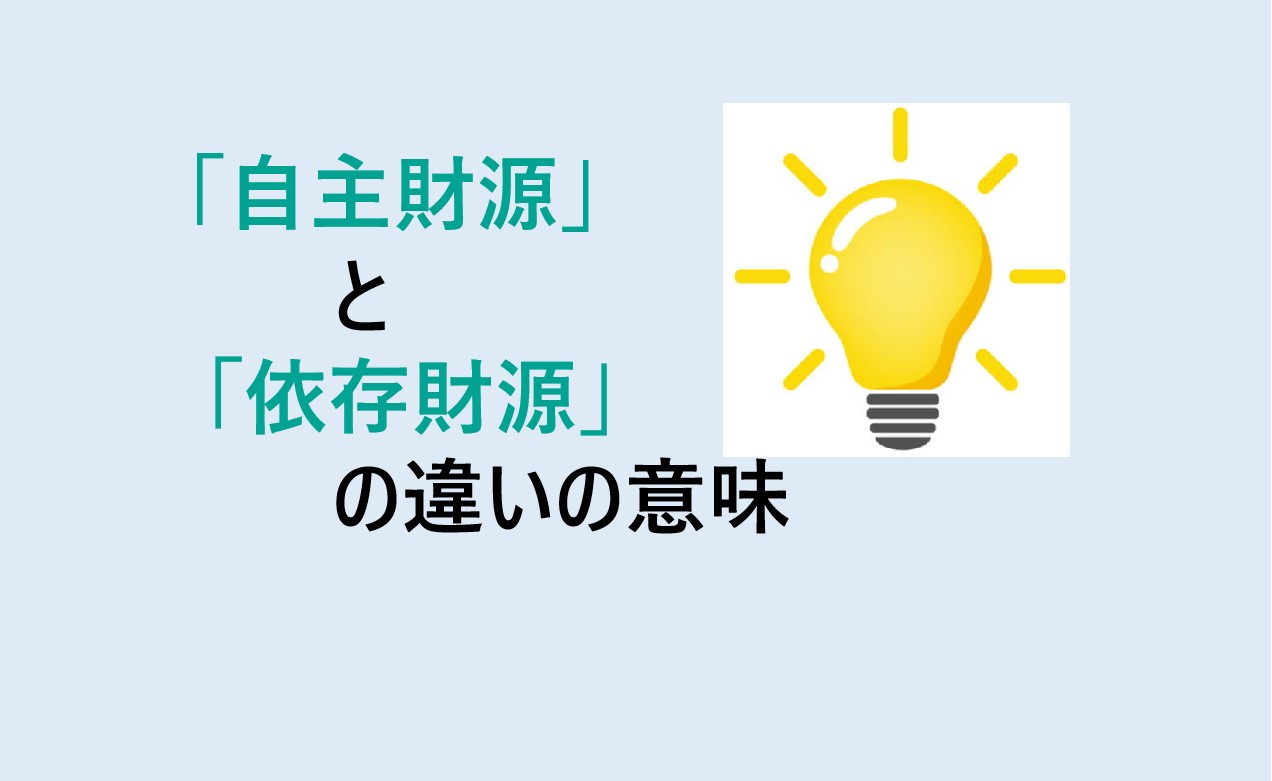地方自治体が安定した行政運営を行うためには、十分な財源の確保が不可欠です。
そこで重要となるのが、自主財源と依存財源という2つの財源の仕組みです。
本記事では、これらの言葉の意味や具体的な使い方、そして自主財源と依存財源の違いについて詳しく解説していきます。
自主財源とは
自主財源とは、地方公共団体が自らの権限で徴収し、自由に使用することができる財源のことを指します。
たとえば、地方税(県税・市税)や公共施設の使用料、自治体が独自に運営する事業の収益などがこれに該当します。
この財源は、外部に依存せずに自治体自らが確保するものであるため、使途の自由度が高く、地域の実情に即した施策や事業を展開するための原資として重宝されます。
ただし、自主財源も完全に自由というわけではなく、税率の変更などには法律や議会の承認が必要であり、一定の制約の中で運用されています。
したがって、自治体の財政の健全性や独立性を示す指標として、この自主財源の割合は非常に重要です。
自主財源という言葉の使い方
自主財源は、地方自治体が主体的に収入を得て、それを地域の運営に活用する際に用いられます。
特に、自治体が独自政策を展開したいときに強調される言葉です。
例:
-
自主財源を活用して地域限定の子育て支援策を導入した。
-
自主財源の比率を上げるために新たな観光施策を始めた。
-
自主財源の少なさが市の柔軟な施策に制限を与えている。
依存財源とは
依存財源とは、地方公共団体が国や都道府県などの上位機関から交付金や補助金として受け取る財源のことを意味します。
たとえば、地方交付税交付金、補助金、負担金などがこれに当たります。
これは、自治体単独ではまかないきれない事業や施策を実施するために、外部の支援として提供されるものであり、ほとんどの場合、用途が定められているのが特徴です。
そのため、自治体が自由に使えるお金ではなく、特定の目的のためにのみ使用することが求められます。
依存財源が多い自治体ほど、自主的な財政運営が難しくなり、国や都道府県の方針に左右されやすい傾向があります。
依存財源という言葉の使い方
依存財源は、外部支援による収入を表す際に使われます。
予算の多くをこの財源に頼っている自治体では、自由な政策実施が難しいことが強調される場面で使用されます。
例:
-
依存財源に頼らず、自主的な財政運営を目指すべきだ。
-
依存財源の増加により、自治体の施策自由度が制限されている。
-
国からの交付金は、典型的な依存財源の一つだ。
自主財源と依存財源の違いとは
自主財源と依存財源の違いは、財源の「獲得方法」と「使用の自由度」にあります。
まず、自主財源は地方公共団体が自ら収入として得たお金です。
地方税や公共料金収入などがこれに該当し、一定の法的制限はあるものの、比較的自由に使用できるという特長があります。
自ら調達するため、工夫次第で増やすことも可能です。
一方、依存財源は国や都道府県から交付されるお金であり、原則として用途が限定されています。
そのため、地方自治体の裁量で使うことはできず、国が推進する政策の実施手段としての性格が強くなります。
このため、自主財源の割合が高ければ高いほど、自治体の独立性が高くなり、独自の政策を展開しやすくなります。
反対に、依存財源に頼る割合が高い場合、自治体の自由度は下がり、外部の方針に左右されやすくなります。
日本全国の地方公共団体における平均的な構成は、自主財源が約60%、依存財源が約40%とされていますが、自治体ごとに大きな差があるのが実情です。
地域経済の発展や税収増によって自主財源を拡充することが、今後の課題とされています。
まとめ
自主財源と依存財源の違いは、自治体の財政運営において非常に重要な要素です。
自主的な運営を可能にするためには、自主財源の比率をいかに高めていくかがカギとなります。
両者の特性と役割をしっかりと理解し、今後の地域づくりに活かしていきましょう。
さらに参照してください:ファントムストックとストックオプションの違いの意味を分かりやすく解説!