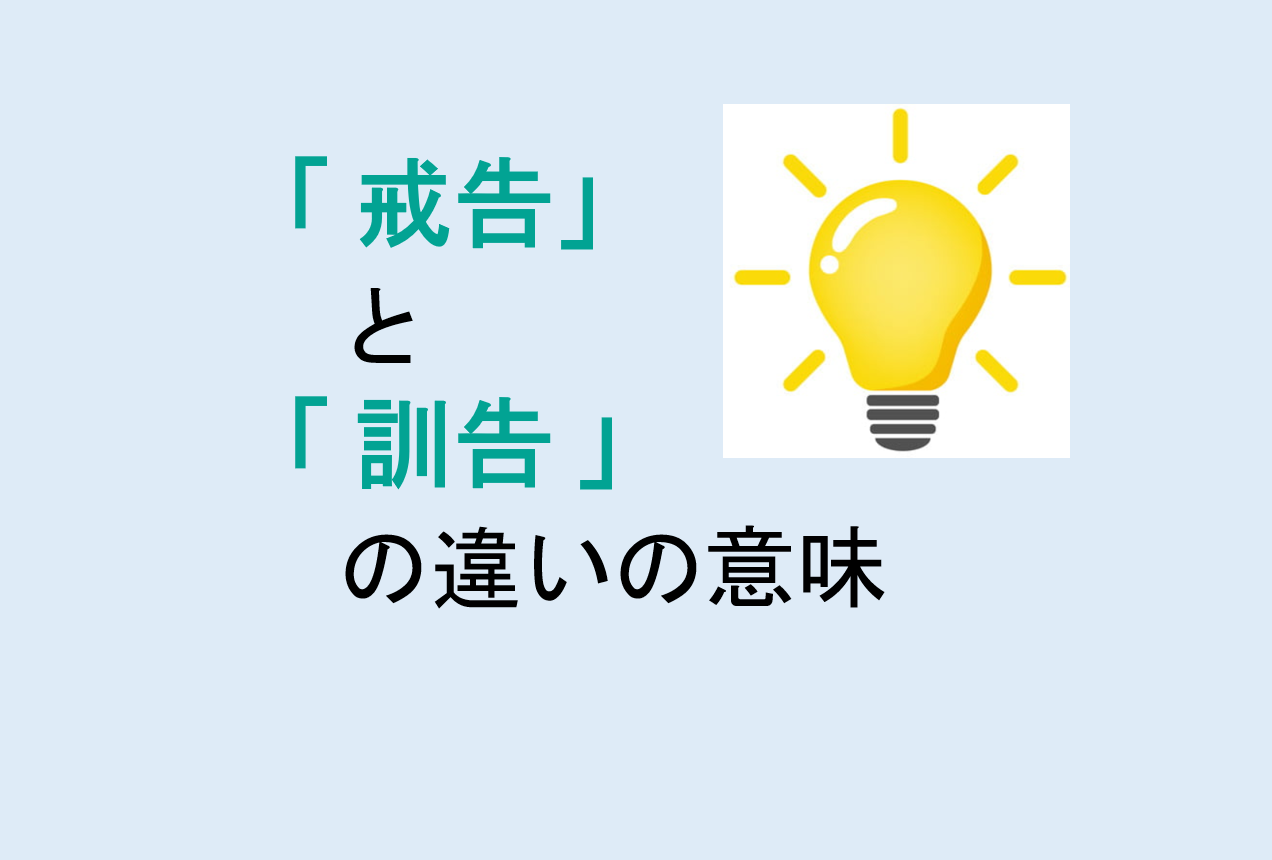会社や公務員の世界では、従業員が規律違反や問題行動を起こした際に「処分」が行われます。
その中でよく耳にするのが戒告と訓告という言葉です。
どちらも注意や指導を意味しますが、処分の重さや法的な位置づけは異なります。
特に戒告は懲戒処分として正式に記録されるのに対し、訓告は会社や状況によって懲戒処分に含まれない場合もあります。
本記事では、戒告と訓告の違いを詳しく解説し、それぞれの意味や使い方、具体例を紹介します。
職場の規律や人事評価に関わる重要なテーマですので、ぜひ最後までご覧ください。
戒告とは
戒告とは、従業員の過失や不適切な行動に対して「強く戒めること」を意味し、懲戒処分の一つとして行われるものです。
方法としては口頭での注意や文書による通知があり、懲戒処分の中では比較的軽い部類に属しますが、正式な処分である点が特徴です。
懲戒処分には、解雇・停職・減給・降格など重いものもありますが、その中で戒告は「厳重注意」にあたる処分と位置づけられています。
軽い処分であっても、記録として残るため昇進や人事評価に影響を及ぼす可能性がある点は無視できません。
また、戒告は民間企業だけでなく、公務員に対しても適用されます。
国家公務員や地方公務員に関しても懲戒処分の一種として規定されており、その妥当性について裁判で争われるケースもあります。
したがって、会社が戒告処分を行う際には、規則に基づいた正しい手続きを踏むことが求められます。
このように戒告は、軽度ながらも正式な懲戒処分であり、従業員に対して強い警告の意味を持つものといえます。
戒告という言葉の使い方
戒告は、職場における懲戒処分の一環として使用されるのが一般的です。
従業員の問題行動に対して「改善を強く求める」際に用いられます。
例:戒告の使い方
-
就業規則違反により従業員に戒告処分が下された。
-
公務員が服務規律違反を理由に戒告を受けた。
-
戒告を受けたことで昇進に影響が出る可能性がある。
訓告とは
訓告とは、「教え告げる」という意味を持ち、従業員の問題行動に対して厳重注意を行うことを指します。
方法は口頭や文書による注意で、会社の就業規則によっては懲戒処分の一つとされる場合もあれば、処分に含まれない場合もあります。
懲戒処分の中では最も軽い位置づけとされ、社員の行動改善を促す目的で行われます。
ただし、公務員の場合には訓告は懲戒処分に含まれない点が特徴です。
公務員の懲戒処分は免職・停職・減給・戒告に限定されており、訓告はそれよりも軽い注意にあたります。
そのため、訓告を受けても基本的には昇進や昇給に直接影響することはありません。
しかし、人が査定を行う以上、訓告を受けたことが間接的に評価に響く可能性はあります。
つまり公式な処分ではなくとも「信頼度が下がる」というリスクがあるのです。
訓告という言葉の使い方
訓告は、比較的軽い注意や指導を表現する際に使われます。
組織内での秩序維持や従業員教育の一環として用いられるのが一般的です。
例:訓告の使い方
-
上司からの度重なる訓告を受け、社員は反省を示した。
-
就業態度に問題があったため、文書で訓告が行われた。
-
訓告は懲戒処分に当たらない場合も多い。
戒告と訓告の違いとは
戒告と訓告の違いは、処分の重さと法的な位置づけにあります。
まず、戒告は必ず懲戒処分に該当し、会社や公務員における正式な処分の一つです。
従業員の過失や不正を強く戒め、記録に残るため人事評価や昇進に影響することがあります。
一方、訓告は必ずしも懲戒処分に含まれるとは限りません。
会社の就業規則によっては処分として扱う場合もありますが、多くは注意指導の位置づけにとどまります。
公務員の場合には訓告は懲戒処分に該当せず、法的な拘束力もありません。
具体的には、従業員が何度も遅刻をした場合、最初は訓告による注意が行われます。
それでも改善が見られない場合に、より重い処分として戒告が下されるのが一般的な流れです。
つまり、訓告は戒告の一歩手前であり、行動改善を促すための警告的な意味合いを持ちます。
このように、戒告は正式な懲戒処分、訓告は比較的軽い注意指導という違いがあり、処分の重さに明確な差が存在します。
まとめ
戒告と訓告の違いを整理すると、戒告は懲戒処分として正式に記録される重い注意であり、人事評価や昇進に影響を及ぼす可能性があります。
一方、訓告は比較的軽い注意や指導であり、必ずしも懲戒処分には含まれません。
両者の大きな違いは「処分の重さ」と「法的な位置づけ」にあると言えるでしょう。
職場での規律や評価に直結するため、正しい理解を持つことは働くうえで非常に重要です。
さらに参考してください: