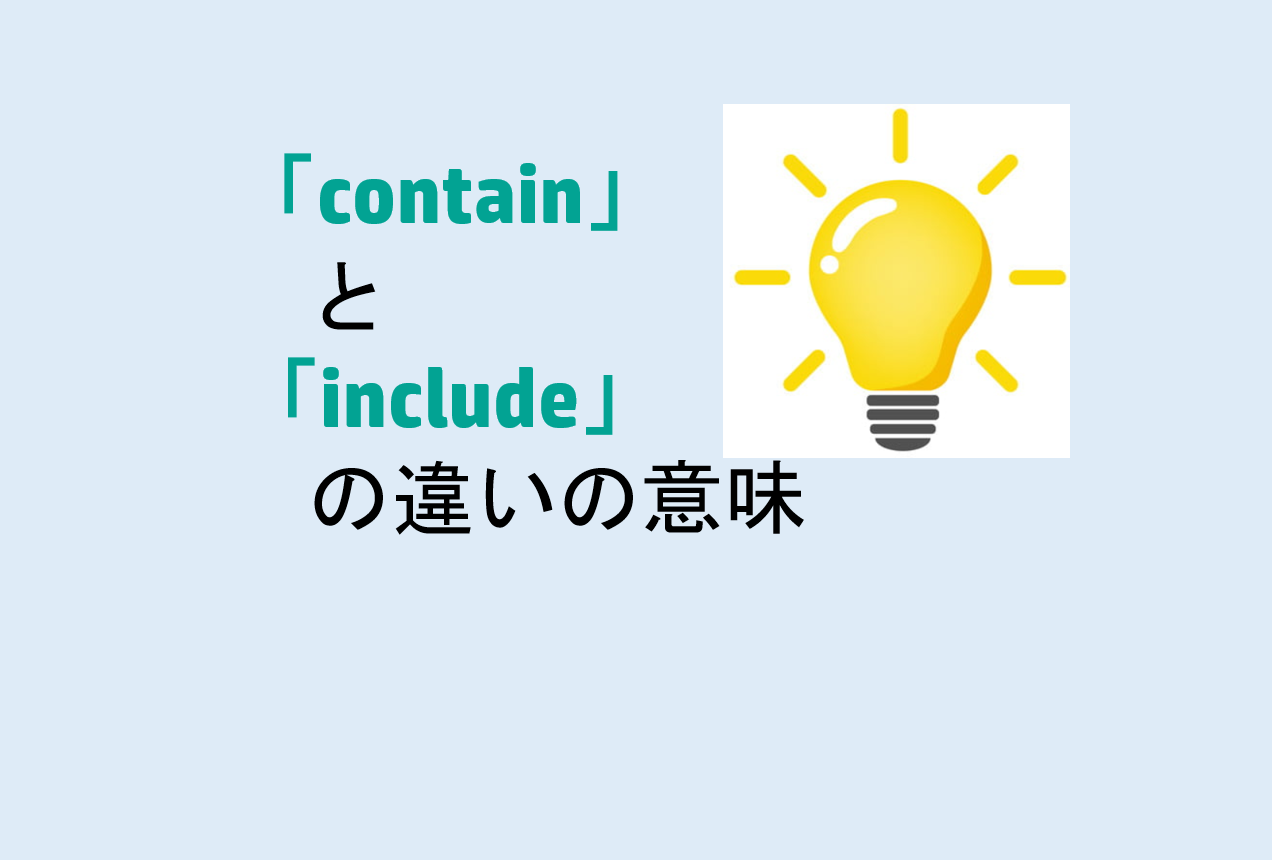英語学習をしていると、containとincludeのように、意味が似ている単語に戸惑うことはよくあります。
どちらも「含む」と訳されることが多いですが、その使い方やニュアンスには明確な違いがあります。
この記事では、containとincludeの違いを明確に解説し、それぞれの意味や具体的な使用シーン、例文を通して分かりやすく紹介します。
英語の正しい理解と自然な表現力を身につけたい方は、ぜひ参考にしてください。
containとは
containは、「〜を含む」「〜を収容する」という意味を持つ動詞で、ある物の中に他の物を物理的に収めるというニュアンスがあります。
語源はラテン語の「com(共に)+tenere(保持する)」で、何かの中にしっかりと収めて保持している状態を表します。
この単語は、物理的・空間的に中に入っている状態を指すことが多く、「容器が液体を含む」「箱が物を収めている」といったシーンで使われます。
たとえば、「container(コンテナ)」という名詞はcontainが語源であり、物を運ぶための大きな容器という意味です。
contain自体は動詞として使われることが多く、名詞形は一般的ではありませんが、名詞として使う場合も文脈次第では成立します。
また、抽象的な内容(怒り・感染症・感情など)を「抑える・封じ込める」といった意味で用いることもあります。
containという言葉の使い方
containは、物理的な入れ物に限らず、データや情報、感情など抽象的な対象にも使われます。
中に含まれている・収められていることを示すため、もともと中に存在している要素を説明する時に使用されます。
例:
-
This box contains old photos.
(この箱には古い写真が入っている) -
This drink contains no sugar.
(この飲み物には砂糖が含まれていない) -
The government is trying to contain the virus.
(政府はウイルスを封じ込めようとしている)
includeとは
includeは、「〜を含む」「〜を含める」という意味で使われる動詞です。
全体の中に一部として何かを含める、加えるというニュアンスがあります。
後から加えられたものや、構成要素の一つとして取り入れられているものを表す時に用いられます。
includeは、情報や項目、人・物などをリストアップするときや、グループの構成を示すときに使われるのが一般的です。
この単語の特徴は、含まれているものが完全ではない可能性があるという点です。
たとえば「The price includes tax.(その価格には税金が含まれている)」のように、他にも要素があるかもしれないことを前提としています。
また、「スマホにアプリが付属している」「料金に食事が含まれている」といった付属・同封されている意味でも使われます。
includeという言葉の使い方
includeは、何かを構成する要素として「一部を取り込む」意味合いで使われます。
特に、「あとから加えられたもの」や「オプション的な付属品」などに用いられます。
例:
-
The meal includes a drink.
(その食事には飲み物が含まれている) -
The price includes tax and service charge.
(料金には税金とサービス料が含まれている) -
The tour includes a free guide.
(このツアーには無料ガイドが含まれている)
containとincludeの違いとは
containとincludeの違いは、「含まれているものの性質」と「その関係性」にあります。
1. 内部に格納されているか
-
containは、あらかじめ物理的または抽象的に中に収められている状態を指します。
内容物が容器の中に完全に入っていることを示します。
-
一方で、includeは、一部として含まれていることを意味し、付属品や構成要素として取り入れられていることを表します。
2. 後付けかどうか
-
containは、もともと中にある(格納されている)ことを前提としています。
-
includeは、後から追加されたり、一部として含まれることを意味し、全体の中に加えるニュアンスがあります。
3. 使われる文脈
-
containは物理的な対象(箱・容器・飲み物など)や抽象的な内容(感情・情報)などが入っている状況に使われます。
-
includeは、価格やサービス内容、リストやグループの構成要素を示すときによく使われます。
比較表

たとえば、スマートフォンのアプリについて言えば:
-
「スマホは多くのアプリをcontainしている」と言えば、それらが内部に物理的に格納されている印象になります。
-
一方、「このスマホには無料アプリがincludedされている」と言えば、あとから付属として加わったものとして表現されます。
このように、同じ対象でも視点を変えると使う動詞が異なってきます。
まとめ
containとincludeの違いは、「含まれているものの本質」と「その含まれ方」にあります。
-
containは、すでに中に格納・内包されている状態を指し、物理的・抽象的な容器や内容に対して使われます。
-
includeは、何かの一部として後から加えられた要素や付属品などを意味し、サービスや項目、構成要素を説明するときに使われます。
似ているようで異なるこれらの単語を正しく使い分けることで、英語表現の精度がぐっと高まります。
場面やニュアンスに応じて、自然な英語を使いこなせるようにしていきましょう。
さらに参考してください: