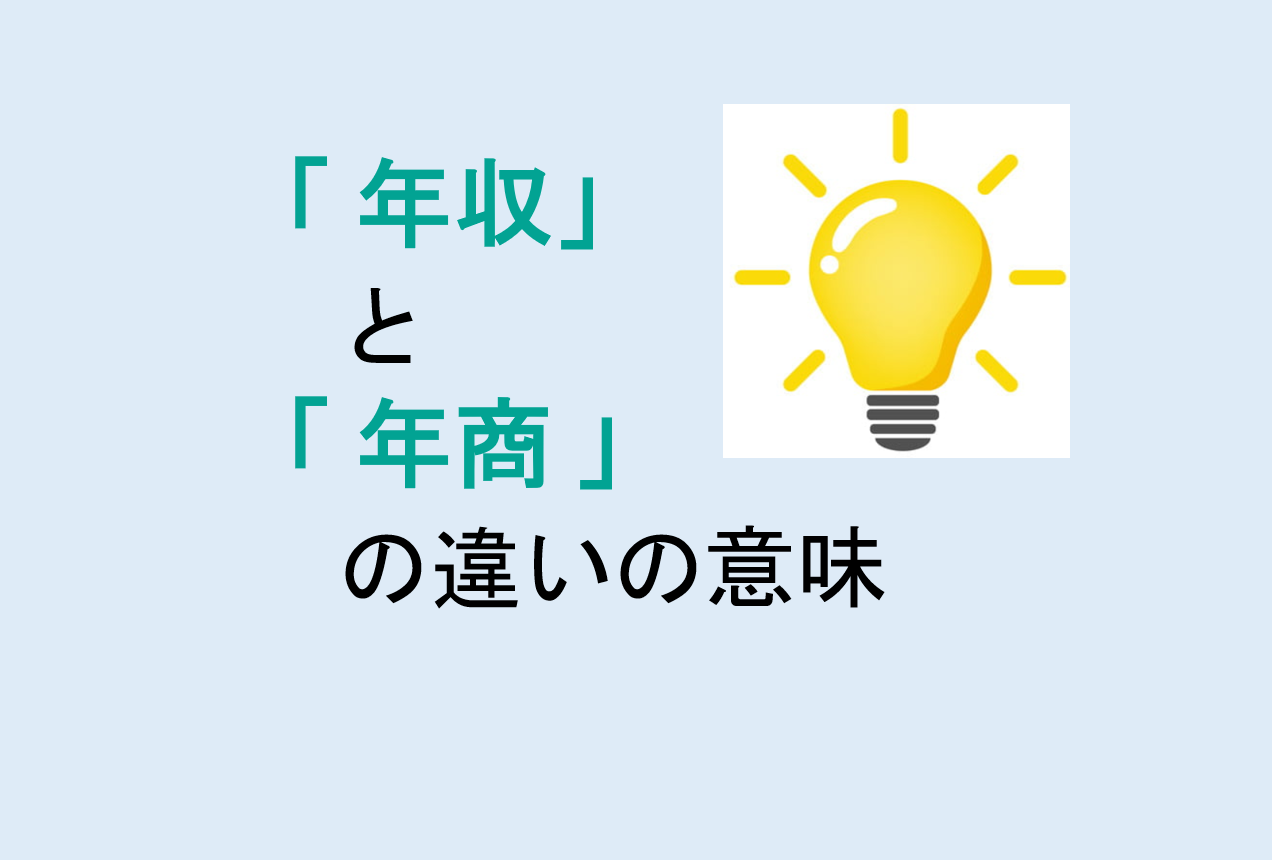お金に関する言葉の中でも、ビジネスや日常会話でよく登場するのが年収と年商です。
一見似ているように感じられますが、この二つは指す対象や意味が大きく異なります。
年収は個人の収入を示す言葉であり、年商は企業の売上高を表します。
特に転職活動や起業を考える際には、両者の違いを正しく理解しておくことが大切です。
本記事では、年収と年商の違いを具体例を交えながら分かりやすく解説します。
年収とは
年収とは、1年間で個人が得た収入の合計を指す言葉です。
会社員の場合、毎月の給与や賞与(ボーナス)の合計が年収になります。
さらに、副業での報酬や株式の配当、事業収入などがある場合は、それらもすべて含めた金額が年収にあたります。
ただし、年収はあくまで額面の収入総額であり、実際に手元に残る金額(手取り)とは異なります。
給与からは社会保険料や年金保険料、所得税などが天引きされるため、手取りは年収より少なくなります。
そのため、求人情報などで「年収500万円」と表記されていても、実際に受け取れる金額はそれより低くなる点に注意が必要です。
また、契約形態によって年収の算出方法も異なります。
例えば、月給制でボーナスがない場合は、12か月分の給与を合計した金額が年収となります。
一般的に年収は個人の収入を表すものであり、企業や団体の規模を示す際には使われません。
年収という言葉の使い方
年収は、個人の生活水準や仕事選びにおいて重要な指標です。
転職活動、ローン審査、ライフプランの設計など、幅広い場面で使われます。
例
-
転職して年収が100万円アップした。
-
年収は低いが、やりがいを感じられる仕事だ。
-
将来のために年収を安定させたい。
年商とは
年商とは、企業が1年間に得た売上高の合計を指します。
商品やサービスを販売して得た金額を合計した数字であり、会計用語では「年間の商いの合計」を意味します。
重要なのは、年商は売上高を表すものであり、利益を直接示すものではないという点です。
売上の中には、原材料費や仕入れ、広告費、人件費などのコストも含まれています。
そのため、年商が高くても経費がかかりすぎれば利益は少なくなります。
例えば「年商1億円」と聞くと大きな規模の会社に感じられますが、経費が9,800万円かかっている場合、利益は200万円しか残りません。
したがって、年商は企業の規模を知る目安にはなりますが、経営状態や収益性を判断するには不十分です。
年商という言葉の使い方
年商は、主に企業の規模や市場における存在感を示す際に使われます。
経済ニュースや経営指標、事業計画などでもよく登場する用語です。
例
-
事業が好調で年商1億円を突破した。
-
年商は高いが、利益率が低いため経営は苦しい。
-
新規事業が軌道に乗り、年商が大幅に伸びた。
年収と年商の違いとは
年収と年商の違いは、対象とする範囲と意味合いにあります。
-
年収は「個人の収入」を表す言葉で、給与や賞与、副業収入などを合計した金額です。
-
年商は「企業の売上高」を表す言葉で、商品やサービスを販売して得た金額の合計です。
両者は似た響きを持ちますが、対象が「個人」か「企業」かで大きく異なります。
個人事業主の場合は、年商と年収を混同しやすい点に注意が必要です。
取引先から得た報酬の合計が年商であり、そこから原材料費や経費を差し引いた残りが年収となります。
例えば、年商1,000万円でも、経費が700万円かかれば年収は300万円になります。
つまり、年収は働き手に実際の利益をもたらす金額を示し、年商は企業の事業規模を示す指標です。
両者を正しく区別することで、収入や企業規模をより正確に理解できるようになります。
まとめ
年収と年商の違いは、対象が個人か企業かにあります。
年収は個人が1年間で得た収入の総額であり、生活水準やライフプランに直結する指標です。
一方、年商は企業が1年間で得た売上の合計であり、会社の規模を測る目安にはなりますが、利益を直接示すものではありません。
特に個人事業主は両者を混同しやすいため、正しい理解が欠かせません。
数字の見かけだけに惑わされず、本質を見極めることが大切です。
さらに参考してください: