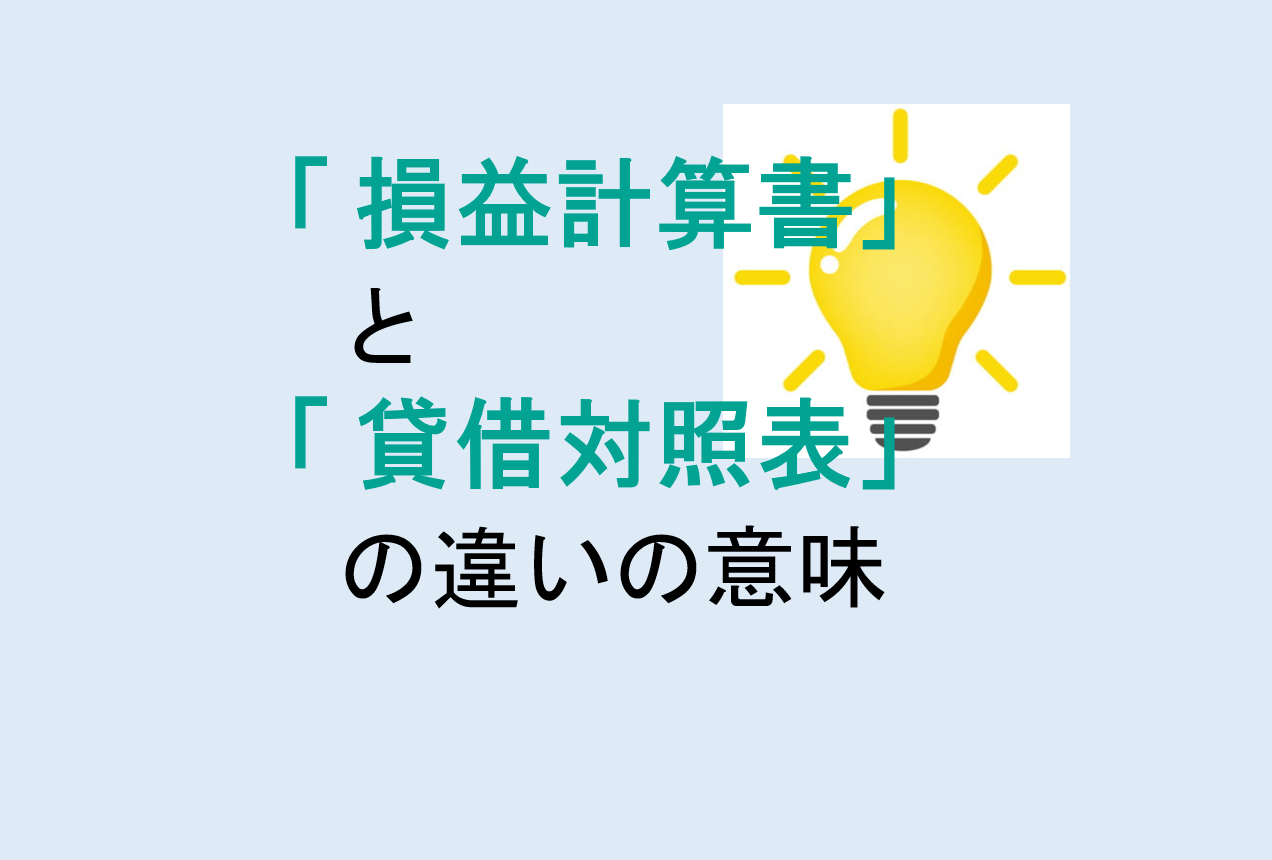企業の財務状況を理解するうえで欠かせないのが、損益計算書と貸借対照表です。
どちらも財務諸表の中心を成す書類であり、経営成績や財政状態を把握するために必ず用いられます。
しかし、この2つは混同されがちでありながら、それぞれ異なる目的と役割を持っています。
この記事では、損益計算書と貸借対照表の定義や使い方、そして両者の違いについて分かりやすく解説します。
損益計算書とは
損益計算書(そんえきけいさんしょ)は、ある一定の会計期間における企業の経営成績を示す書類です。
英語では「Profit and Loss Statement」と呼ばれ、略してP/Lとも言われます。
この書類では、期間中に発生した収益と費用を集計し、その結果として企業がどれだけ利益を得たのか、あるいは損失を出したのかを明らかにします。
つまり、企業が「儲かったか」「赤字か」を把握できる重要な財務諸表です。
損益計算書に記載される主な項目は以下の通りです。
-
売上高から売上原価を差し引いた「売上総利益」
-
売上総利益から人件費や広告費、減価償却費などを差し引いた「営業利益」
-
営業利益に営業外収益や営業外費用を加減した「経常利益」
-
経常利益に特別利益や特別損失を加減した「税引前当期純利益」
-
そこから法人税等を控除した「当期純利益」
このように、損益計算書は1年間や四半期といった「期間の経営成績」を測るために作成される点が大きな特徴です。
損益計算書という言葉の使い方
損益計算書は企業の収益性や経営の健全性を評価する場面で用いられます。
投資家や経営者が企業の収益力を把握するための基本資料です。
例:損益計算書の使い方
-
投資家は損益計算書を確認して企業の利益構造を分析する。
-
決算発表では損益計算書に基づいて業績が報告される。
-
経営者は損益計算書をもとに来期の収益目標を立てる。
貸借対照表とは
貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう)は、ある特定の時点における企業の財政状態を示す書類です。
英語では「Balance Sheet」と呼ばれ、略してB/Sと表されます。
貸借対照表の特徴は、「ある一時点での財産の状態」を把握できる点です。
そこには、企業が保有する資産や抱えている負債、そして純資産が整理されて記載されています。
貸借対照表は大きく次の3つの区分で構成されます。
-
資産の部:現金や売掛金などの流動資産、土地や建物といった固定資産、繰延資産など
-
負債の部:買掛金や未払金などの流動負債、長期借入金や退職給付引当金などの固定負債
-
純資産の部:資本金、利益剰余金、その他有価証券評価差額金など
これらを一覧化することで、「会社にどれだけの資産があり、それがどのような負債や資本で成り立っているのか」を把握できます。
したがって、貸借対照表は企業の安全性や財務健全性を判断する際に非常に重要な資料です。
貸借対照表という言葉の使い方
貸借対照表は資産や負債の状況を把握したり、財務の安定性を分析する際に使われます。
金融機関や投資家が信用力を判断するために必ず確認する書類です。
例:貸借対照表の使い方
-
銀行は融資を行う前に企業の貸借対照表をチェックする。
-
投資家は貸借対照表を分析して企業の財務体質を評価する。
-
経営会議では貸借対照表を用いて資金調達の方針を決定する。
損益計算書と貸借対照表の違いとは
損益計算書と貸借対照表はどちらも財務諸表であり、企業の経営状況を把握するうえで欠かせません。
しかし、両者の目的や記載内容には明確な違いがあります。
まず、損益計算書は「一定期間における収益と費用を集計し、利益または損失を算出する書類」です。
企業がその期間にどれだけ儲けたのか、あるいは損をしたのかを表す役割を持ちます。
売上や費用の動きを明確にするため、経営成績を評価するのに適しています。
一方、貸借対照表は「ある特定の時点における財産の状態を表す書類」です。
企業の資産、負債、純資産がどのようなバランスで存在しているかを示し、財政の健全性を確認するために利用されます。
両者の関係を分かりやすく言えば、損益計算書が「企業の成績表」であるのに対し、貸借対照表は「企業の健康診断書」ともいえます。
前者は期間的な収益力を、後者はある時点での安全性や安定性を表しているのです。
このように、両者は目的や視点が異なるものの、相互に補完し合う存在です。
企業の経営状態を正しく理解するには、損益計算書と貸借対照表の両方を合わせて分析することが欠かせません。
まとめ
損益計算書は一定期間の利益や損失を表す書類であり、企業の収益力や経営成績を把握するために用いられます。
これに対して、貸借対照表は特定時点の財政状態を示す書類で、企業の安全性や資産状況を把握する目的があります。
両者は会計の基礎を成す重要な資料であり、それぞれの役割を理解することで、より正確に企業の経営状況を判断できるでしょう。
さらに参考してください: