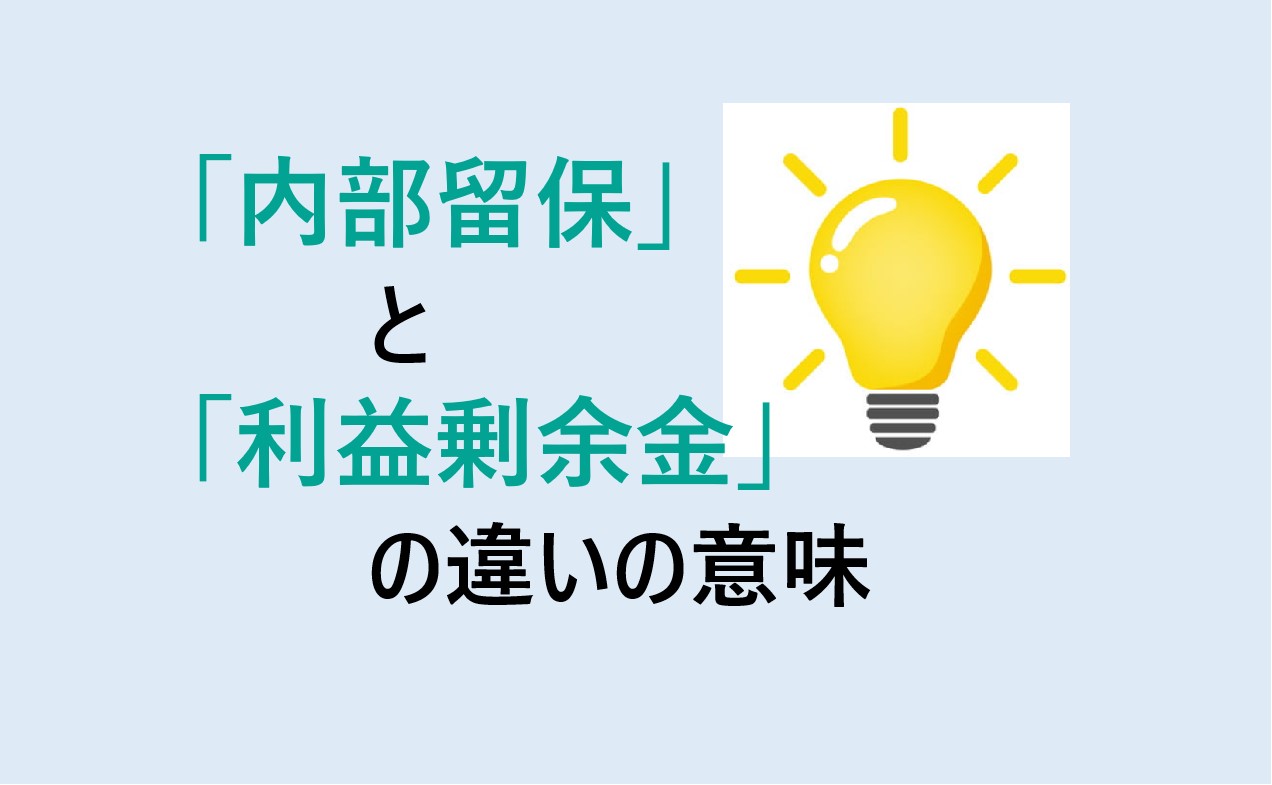企業の財務や会計の話題でよく出てくる言葉に「内部留保」と「利益剰余金」があります。
どちらも会社の利益に関わる重要な概念ですが、混同されやすい言葉でもあります。
本記事では、両者の意味や使い方、そして内部留保と利益剰余金の違いについて、誰でも分かりやすく解説していきます。
内部留保とは
内部留保(ないぶりゅうほ)とは、企業が生み出した利益のうち、株主への配当や税金などの社外への支払いを差し引いた後に、社内にとどめて蓄える部分のことを指します。
これは企業が将来の投資や不測の事態に備えるための資金として保有する金額です。
具体的には、企業は製品やサービスを提供して利益を得ますが、その利益全てを配当するわけではありません。
その一部を社内に留保することによって、経営の安定性を確保します。
たとえば、業績が悪化した時期でも、内部留保があればその損失をカバーし、倒産を回避することも可能になります。
内部留保には、「利益準備金」や会社の判断で積み立てる「任意積立金」などが含まれます。
これらの蓄えがあることで、企業は経済の変動にも強くなり、継続的な成長が見込めるのです。
内部留保という言葉の使い方
内部留保は、企業が利益を再投資または将来に備えて社内にとどめておく場合に使われます。
財務戦略や経営判断の文脈でよく使用される用語です。
例:
-
経営の安定性を保つために内部留保を積極的に行っている。
-
新工場建設の資金は内部留保から充てる予定だ。
-
内部留保の使い道が問題視されることもある。
利益剰余金とは
利益剰余金(りえきじょうよきん)とは、企業の利益処分によって社内に蓄えられた金額のことを指します。
これは、利益準備金、繰越利益剰余金、任意積立金などから構成されており、企業の株主資本の一部として計上されます。
利益剰余金は、企業会計上の正式な勘定科目であり、企業が上げた利益をどのように処分したかの結果として現れるものです。
企業はこの資金を使って、社員の給与の増額、設備投資、将来的な経営戦略への活用など、多様な用途に充てることができます。
また、利益を配当せずに社内に蓄える「内部留保」を行うことで、その結果として蓄積されていく資金が利益剰余金になります。
このように、利益剰余金は企業の成長と安定を支える重要な資源なのです。
利益剰余金という言葉の使い方
利益剰余金は、決算書や財務諸表などの会計資料で頻繁に使用され、企業の健全性や成長性を示す指標の一つとして重視されます。
例:
-
決算書で利益剰余金の増加が確認された。
-
利益剰余金を使って新規事業に投資する。
-
企業の自己資本比率は利益剰余金の蓄積によって高まる。
内部留保と利益剰余金の違いとは
内部留保と利益剰余金の違いは、主にその定義と会計上の扱いにあります。
まず内部留保は、企業が得た利益から社外に流出する配当金や税金などを差し引いた後に、社内にとどめておく金額を意味します。
企業が景気の変動や将来の投資に備えて確保しておくためのもので、倒産リスクの軽減にもつながります。
一方の利益剰余金は、会計上の正式な科目であり、内部留保によって社内に蓄えられた利益の合計額を指します。
つまり、内部留保によって形成された資金が利益剰余金という会計項目で表示されるという関係です。
言い換えれば、内部留保は概念的な言葉であり、企業活動の実態を表すのに使われるのに対し、利益剰余金はその結果として決算書上に明記される具体的な数字です。
さらに、内部留保は法律上の正式な用語ではありませんが、利益剰余金は会計や税務で正式に定められた用語という違いもあります。
まとめ
本記事では、内部留保と利益剰余金の違いについて詳しく解説しました。
どちらも企業の利益管理において重要な概念ですが、意味や使い方に明確な違いがあります。
内部留保は企業が利益を社内に保留する行為そのものを指し、利益剰余金はその結果として蓄積された金額を表します。
この違いを理解することで、企業の財務戦略や経営判断をより深く読み解くことができるでしょう。
さらに参照してください:売掛金と買掛金の違いの意味を分かりやすく解説!