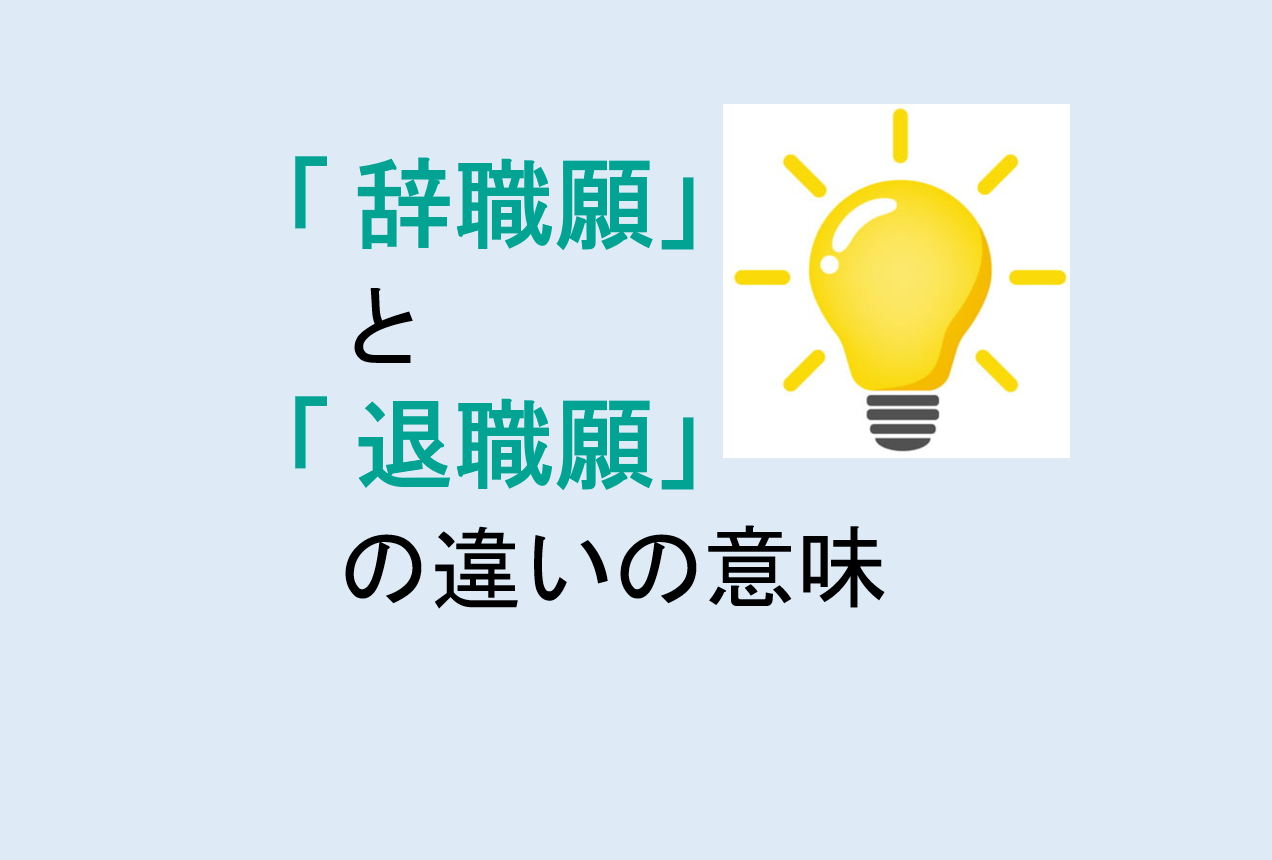社会人であれば一度は耳にする 辞職願 と 退職願。
どちらも「会社を辞めたい」という意思を示す書類ですが、実は使われる対象や意味が異なります。
役職や立場によって適切な表現があり、誤って使用すると相手に違和感を与える可能性もあります。
本記事では、辞職願と退職願の正しい意味と使い方の違いを分かりやすく解説します。
両者の特徴を理解することで、自分の立場に合った適切な書類を提出できるようになりましょう。
辞職願とは
辞職願 とは、主に役職に就いている人や公務員が、自らの意思で職を辞めたいと申し出る際に提出する書類を指します。
ここで重要なのは、「辞職」が一般社員やアルバイトなど役職を持たない立場には通常使われないという点です。
例えば、会社の管理職や課長・部長といった役職者、または国家公務員や地方公務員が職を辞する場合には、辞職願を提出するのが一般的です。
辞職願は、自らの意思による「労働契約の解消」を意味しており、提出後に受理されると効力が発生します。
さらに注意すべきなのは、一度受理された辞職願は基本的に撤回ができない点です。
これは、労働者が一方的に契約解消を申し入れる形式に当たるためであり、会社側に受け入れられた時点で退職が確定するのです。
そのため、提出する際には慎重な判断が必要となります。
辞職願という言葉の使い方
辞職願 は、役職者や公務員が自ら退く意思を正式に表明する際に使用されます。
通常の社員が用いると不自然になるため、対象者が限定されているのが特徴です。
また、その効力は強く、一度受理されれば撤回不可能である点もポイントです。
辞職願の使い方の例
-
過失の責任を取るため、部長が辞職願を提出した。
-
公務員が不祥事の責任を取り、辞職願を上司に差し出した。
-
辞職願が受理された時点で、契約関係は終了する。
退職願とは
一方、退職願 とは、一般企業に勤める役職を持たない社員やアルバイト、パートが会社を辞めたいと申し出る際に使う書類です。
こちらは広く一般の労働者が対象であり、日常的に最も多く使われる退職関連の文書です。
退職願は労働契約の「合意解約」の申し込みにあたり、提出しても必ずしもすぐに効力が発生するわけではありません。
受理されなければ撤回の余地が残るため、比較的柔軟性がある点が辞職願との大きな違いです。
また、退職願は自己都合退職の場合に使われるのが一般的ですが、会社都合によるものや希望退職を募る場合にも形式上提出することがあります。
そのため、労働環境や契約内容に応じて多様な場面で使用されます。
退職願という言葉の使い方
退職願 は、会社員やアルバイトなど役職を持たない人が労働契約を終了したいときに用いられます。
また、受理前であれば撤回が可能な点から、状況次第で柔軟に対応できる特徴があります。
退職願の使い方の例
-
個人的な都合により、退職願を人事部に提出した。
-
退職願はまだ受理されていなかったため、撤回することができた。
-
会社都合退職の場合でも形式上は退職願を提出することがある。
辞職願と退職願の違いとは
辞職願 と 退職願 の最大の違いは、対象者の立場と効力にあります。
辞職願は、役職者や公務員など特定の立場の人が使用し、一度受理されると撤回が不可能です。
つまり、責任ある立場の人が自らの意思で職を辞するための強い効力を持つ文書といえます。
一方、退職願は一般の労働者が用い、提出後も受理されなければ撤回できる点が特徴です。
こちらは労働契約を合意解消するための申し出であり、状況に応じて柔軟に対応できる仕組みになっています。
つまり、辞職願は「役職や公務員が辞めるための最終的な意思表示」であり、退職願は「一般社員が辞めたいときの申し出」という位置付けになります。
誤って使うと相手に違和感を与えるだけでなく、自分の意思表示として不正確になってしまう可能性もあるため注意が必要です。
まとめ
辞職願 は役職者や公務員が職を辞する際に提出する強い効力を持つ書類であり、受理されれば撤回できません。
対して、退職願 は一般労働者が用いるもので、受理されるまでは撤回が可能です。
両者は似ているようで対象や効力が異なるため、自分の立場に合った正しい言葉を選んで使用することが大切です。
正しく理解することで、退職時の手続きがより円滑に進むでしょう。
さらに参考してください: