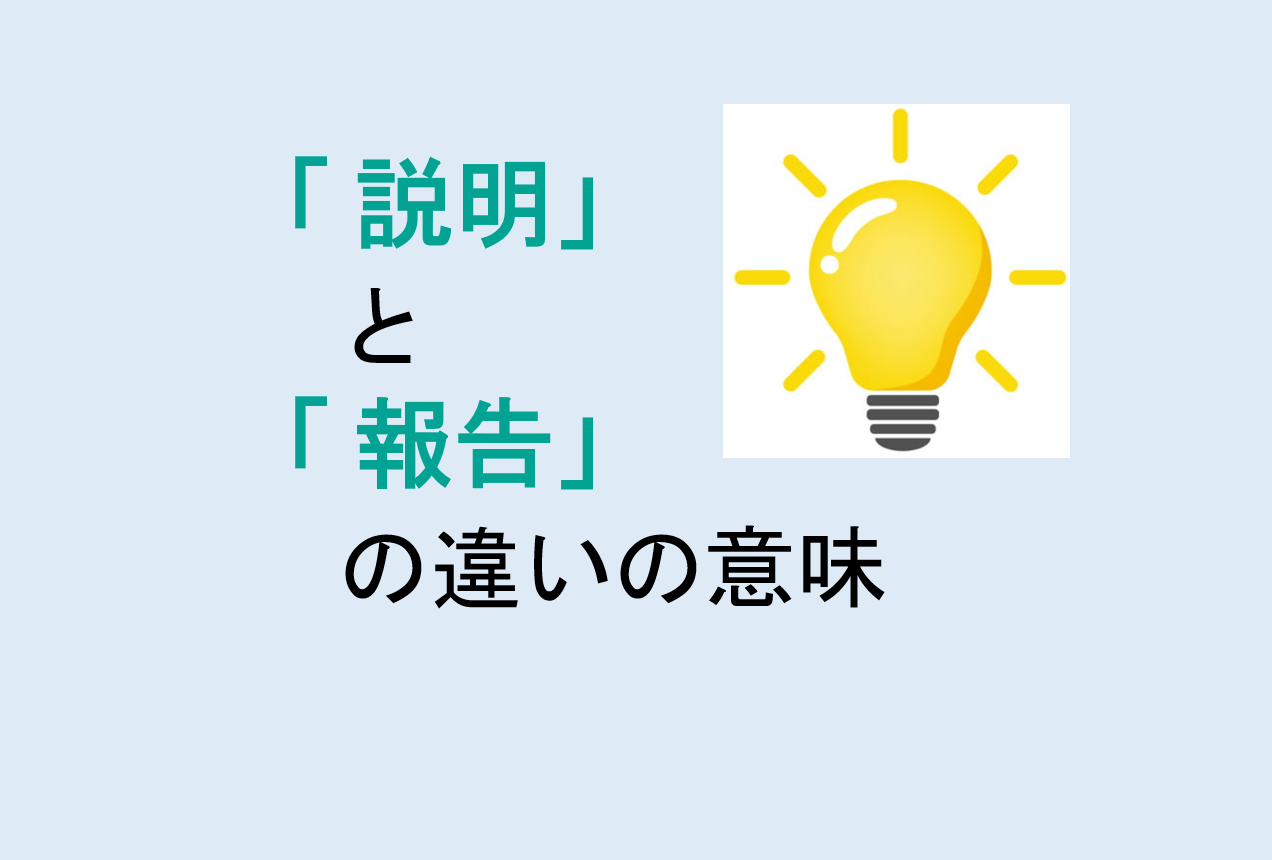日常生活やビジネスシーンにおいて、説明と報告という言葉はよく耳にします。
どちらも「相手に物事を伝える」という点では共通していますが、実は意味や使い方には明確な違いがあります。
正しく理解していないと、場面によっては不適切な言い回しとなり、相手に失礼にあたることもあります。
本記事では、説明と報告の違いや正しい使い方を具体例とともに解説し、社会人として知っておきたい日本語の使い分けを分かりやすく紹介します。
説明とは
説明とは、ある物事や出来事を相手に理解してもらうために、筋道を立てて詳しく伝えることを意味します。漢字の「説」には「筋道を立てて述べる」という意味があり、その本質は「相手に理解させること」です。
例えば、学校の授業で先生が生徒に内容を伝えるときや、親が子どもに状況をわかりやすく話すとき、会社で不祥事について説明を求められる場面など、多くのシーンで使用されます。
また、試験問題でも「〇〇について説明せよ」といった形で頻出する言葉です。
このように説明は「相手が理解できるように話すこと」に重点があり、日常生活からビジネスまで幅広く使われる、非常に一般的な言葉です。
その一方で、「説明して」という言葉にはやや厳しい響きがあるため、子どもや目上の人に対しては「わかるように教えてください」など柔らかい表現に言い換えるのが適切です。
説明という言葉の使い方
説明は、相手に理解を促す必要があるときに使われます。
状況や背景を丁寧に伝えるときに適しており、特に相手がその内容を知らない、または理解していない場合に多用されます。
日常的にも使える便利な言葉ですが、場合によっては厳しい印象を与えるため、言葉遣いに配慮することが大切です。
例:説明の使い方
-
どうしてこのような結果になったのか、詳しく説明してください。
-
彼は会議での説明を怠ったため、上司に注意を受けた。
-
テストでは「この現象について100字以内で説明せよ」と出題された。
報告とは
報告とは、過去に起きた出来事や結果を、義務や責任をもって伝えることを意味します。
漢字の「報」には「知らせる」「むくいる」、「告」には「つげる」という意味があり、特にビジネスや公的な場でよく使われる言葉です。
例えば、会社で上司に業務の進捗を伝える「業務報告」や、研究活動の途中経過をまとめる「中間報告」などがあります。
ここで重要なのは、報告には「伝える義務」が含まれている点です。
そのため、日常会話で友人同士が「報告して」と言うことはあまりなく、通常は「教えて」や「伝えて」と表現する方が自然です。
また、報告は基本的に「過去に起きたこと」に対して行うものであり、未来の出来事に対して使うことはできません。
この特徴も説明との大きな違いのひとつです。
報告という言葉の使い方
報告は、主にビジネスや学術的な場面で、責任や義務を伴って情報を伝えるときに使われます。
目上の人に対して「ご報告お願いします」と表現することもありますが、この場合、上下関係を前提とした言葉遣いとなるため、状況に応じて「お知らせください」といった表現に言い換える方が丁寧です。
例:報告の使い方
-
部下は30ページにも及ぶ業務報告書を作成して提出した。
-
昨日は課長に業務終了の報告を忘れてしまった。
-
会議での決定事項について、速やかに報告してください。
説明と報告の違いとは
説明と報告はどちらも「相手に伝える」行為ですが、目的と使われる場面が大きく異なります。
まず、説明は「相手に理解させること」が目的です。
状況や理由を筋道立てて述べるため、教育、日常会話、ビジネスなど幅広いシーンで使われます。
相手がまだ知らないことや理解していないことに対して行うのが特徴です。
一方、報告は「すでに起きた出来事を責任をもって伝えること」が目的です。
義務的なニュアンスを含むため、ビジネスや研究の場など、公式で上下関係のある環境でよく使われます。
伝える対象は基本的に目上の人や組織であり、対等な関係や親しい関係では「教える」などに言い換える方が自然です。
さらに、説明は未来の出来事や仮定の話についても用いることができますが、報告は過去に起きた事実に限定されるという点も大きな違いです。
まとめると、説明は「理解を促すための伝達」、報告は「義務として事実を伝える行為」であり、この使い分けを誤ると相手に違和感を与える可能性があります。
特に社会人にとっては、両者の違いを正しく理解し、シーンに応じた使い分けを心がけることが重要です。
まとめ
説明と報告はどちらも「相手に物事を伝える」という点で共通していますが、説明は「理解させること」、報告は「義務として事実を伝えること」といった違いがあります。
日常では説明が多く使われ、ビジネスや学術的な場では報告が重視される傾向にあります。
両者の違いをしっかり理解して使い分けることで、相手に正しく意図が伝わり、円滑なコミュニケーションが可能になります。
さらに参考してください: