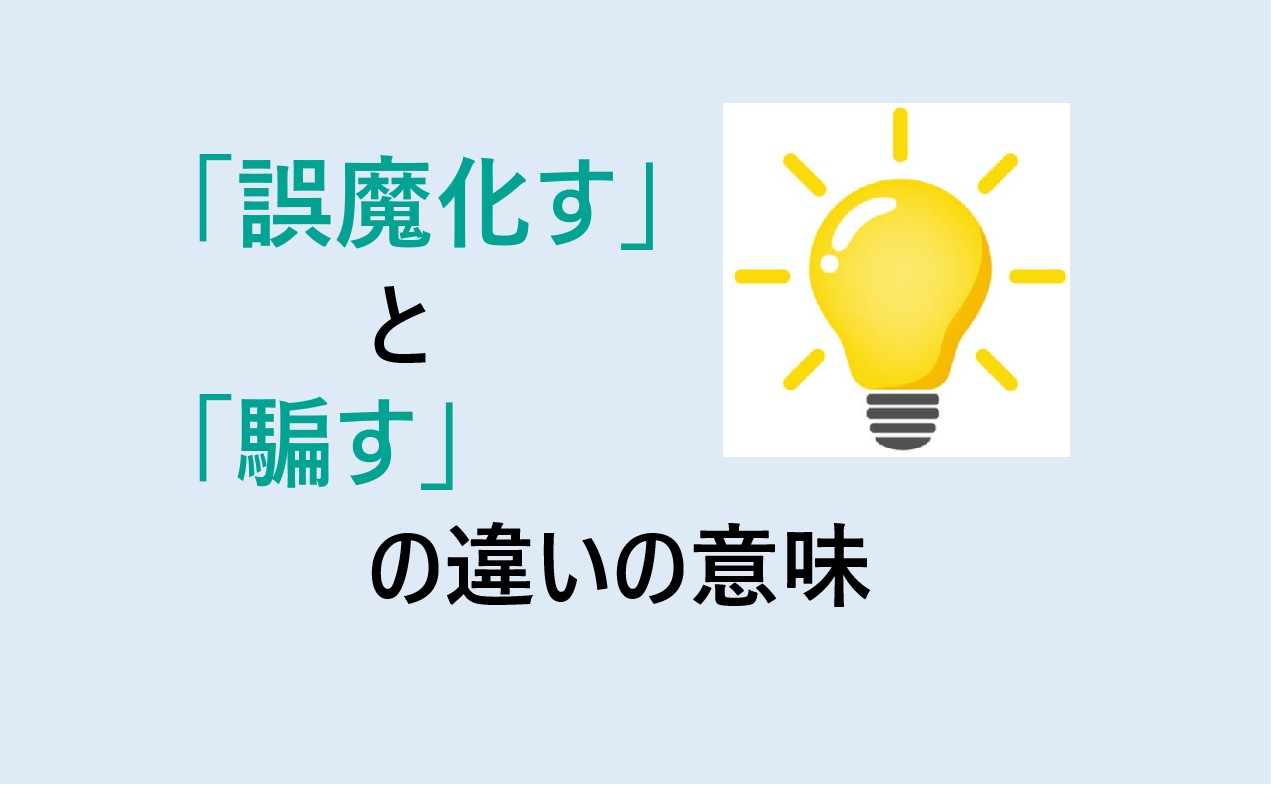日常会話やニュース、ビジネスの場面でも耳にすることが多い「誤魔化す」と「騙す」という言葉。
一見すると似ているように思えるこの二つの言葉ですが、実はその意味や使い方には明確な違いがあります。
この記事では、誤魔化すと騙すの違いを徹底的に解説し、それぞれの使い方や例文も紹介します。
誤魔化すとは
誤魔化す(ごまかす)とは、真実や本心を隠したいときに、話題をそらしたり出まかせを言ったりして、相手の追及から逃れる行為を指します。
例えば、やましいことがあったり、知られたくない事実を隠すために「それっぽく」取り繕う行動です。
この言葉は、相手に嘘を信じ込ませるというよりも、「気づかれないように避ける」「曖昧にする」ようなニュアンスを含んでいます。
漢字では「誤魔化す」または「胡麻化す」と書かれますが、どちらも当て字であり、本来の語源は「化かす(ばかす)」に由来するとされています。
これは「人の心を惑わせる」ことを意味し、まさに誤魔化す行動の核心を表しています。
誤魔化すという言葉の使い方
誤魔化すは、特に自分の過ちや不都合な事実が明らかになりそうな場面でよく使われます。
人に対して使うのはもちろん、自分自身の行動を説明するときにも使用されます。
また、「煙に巻く」などの類義語と同じ文脈で使うこともあります。
例:誤魔化すを使った例文
-
彼は質問に答えずに話を逸らして、上手く誤魔化した。
-
子どもがおつりをごまかそうとしていたのを見逃さなかった。
-
上司にミスを指摘されたとき、とっさに誤魔化そうとしてしまった。
騙すとは
騙す(だます)は、「嘘をついて相手を信じ込ませる」行為を意味します。
相手に虚偽の情報を信じさせることで、自分に有利な状況を作ることが目的です。
この言葉は、「誤魔化す」とは異なり、意図的かつ積極的に相手を欺くという悪意のあるニュアンスが強く含まれます。
たとえば、詐欺や偽情報によって金品を搾取するような行為、または人の感情を利用して騙すような恋愛詐欺などが当てはまります。
場合によっては、法律的にも罰せられるような行為として扱われることもあります。
騙すという言葉の使い方
騙すは、人を欺いて誤信させる場面で使用されます。
人間関係、ビジネス、恋愛、詐欺など幅広いシーンで用いられます。
また、機械などに対して「騙し騙し使う」といった表現で使われることもあります。
これは「なんとかうまく続ける」という意味合いです。
例:騙すを使った例文
-
オレオレ詐欺に騙された高齢者が増えている。
-
彼は人を騙して金をだまし取る常習犯だ。
-
コピー機を騙し騙し使い続けているが、そろそろ限界だ。
誤魔化すと騙すの違いとは
誤魔化すと騙すの違いは、目的と手段の性質にあります。
まず、誤魔化すは「ばれないようにする」「気づかれないように取り繕う」という防御的な行動です。
嘘をつかなくても成り立ちます。たとえば、ミスを指摘されて焦り、話題を逸らすことでその場をしのぐ行為などが該当します。これは、「逃れる」ための行動です。
一方、騙すは「嘘を使って相手をあざむく」という攻撃的な行動です。
虚偽の事実を本当のように装って、相手を操る意図が明確に存在します。
つまり、「信じ込ませて得をする」ための行動です。
また、英語では「誤魔化す」は “bluff” や “evade” などの言葉が使われ、「騙す」は “deceive” や “cheat” が使われます。
英語でもニュアンスが異なっており、両者は明確に区別されていることがわかります。
このように、誤魔化すと騙すの違いは、「逃げるためのごまかし」か、「得をするための嘘」かという、意図の違いにあります。
まとめ
この記事では、誤魔化すと騙すの違いについて詳しく解説しました。
誤魔化すは真実を隠すためにその場を取り繕う行為であり、騙すは嘘を用いて相手を欺く行為です。
それぞれの言葉を正しく理解し、適切な場面で使い分けられるようにしましょう。
さらに参照してください:合宿と遠征の違いの意味を分かりやすく解説!