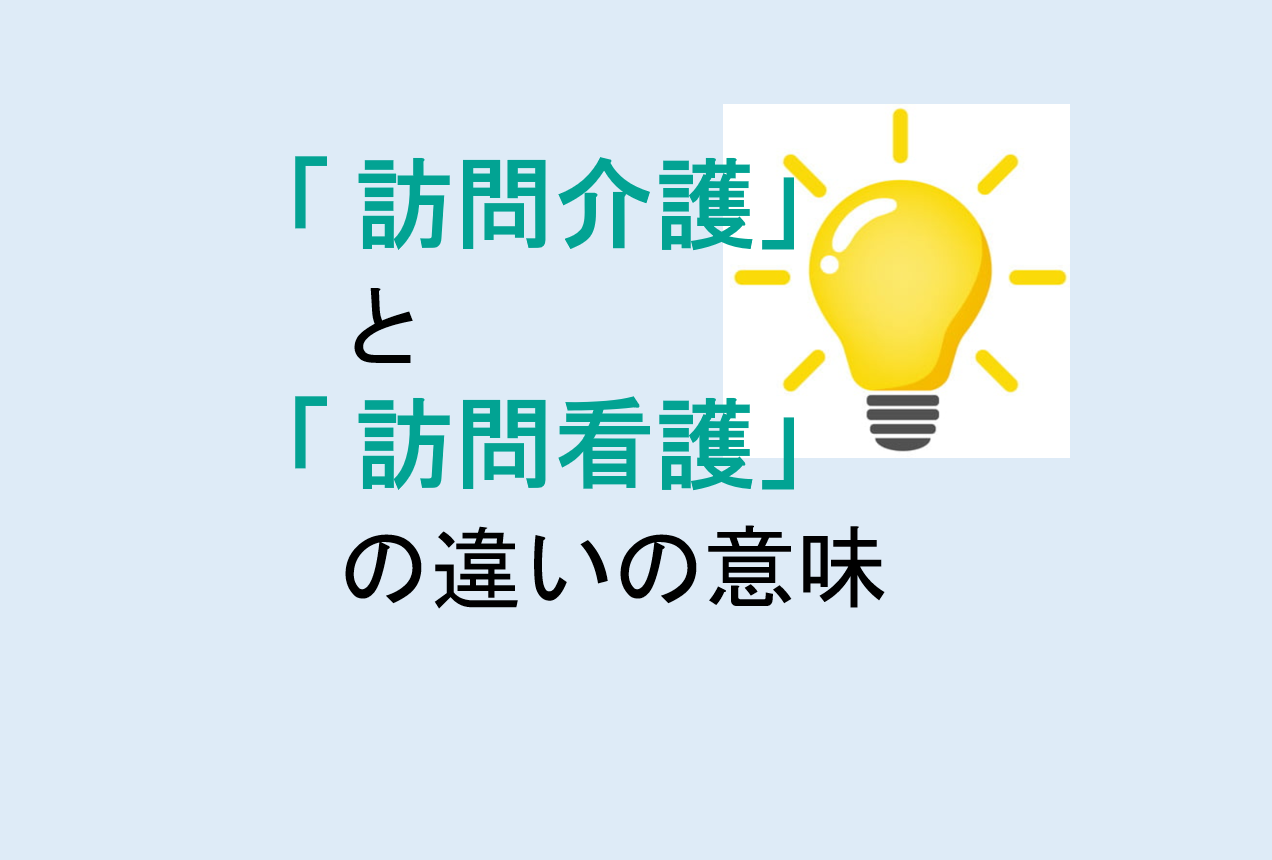高齢化が進む現代社会において、自宅で安心して生活を続けるためのサポートとして注目されているのが訪問介護と訪問看護です。
名前が似ているため混同されがちですが、実際には提供するサービスや関わる専門職、対象となる人の状態に明確な違いがあります。
本記事では、両者の定義や使い方を具体的に解説しながら、訪問介護と訪問看護の違いを分かりやすくまとめました。
介護サービスを検討している方や医療・福祉に関心のある方に役立つ内容です。
訪問介護とは
訪問介護とは、介護が必要な高齢者や要支援者の自宅を、ホームヘルパーや介護福祉士などの介護専門職が訪問し、日常生活を支援するサービスを指します。
漢字の通り「訪問」=自宅を訪れる、「介護」=生活を介助するという意味を持ち、介護保険サービスの中核をなす存在です。
訪問介護の内容は大きく2つに分けられます。
ひとつは食事、入浴、排泄などの身体介護で、もうひとつは掃除、洗濯、買い物、調理などの生活援助です。利用者ができない部分を補うことで、自宅での生活を継続できるよう支える役割があります。
また、訪問介護は医療行為を行うサービスではありません。
そのため、医師の処置や看護師による医療ケアが必要な場合は別途訪問看護が必要になります。
訪問介護は、あくまで生活面の支援に特化している点が特徴です。
訪問介護という言葉の使い方
訪問介護は、介護職員が利用者の自宅を訪れて生活支援や身体介護を行うサービスを指すときに使われます。介護保険制度の中で利用される公的な言葉でもあり、日常的には「ヘルパーさんが来てくれるサービス」という意味で用いられることが多いです。
例:訪問介護の使い方
-
祖母が要介護認定を受け、訪問介護サービスを利用することになった。
-
訪問介護では入浴や食事のサポートを受けられる。
-
訪問介護員が週に数回来てくれるので安心できる。
訪問看護とは
訪問看護とは、病気や障害を持つ在宅療養者のもとへ、看護師や保健師などの医療従事者が訪問し、医師の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助を行うサービスです。
文字通り「訪問」=自宅を訪れる、「看護」=医療的ケアを行うことを意味しています。
訪問看護で提供されるサービスには、バイタルチェック(体温・血圧・脈拍の測定)、服薬管理、点滴、カテーテル管理、床ずれ予防、リハビリなどが含まれます。
利用者本人だけでなく、家族への介護指導や心理的支援も大きな役割です。
病院での治療を続けるのが難しい人や、自宅での療養を望む人にとって、訪問看護は生活の質を維持するために欠かせない在宅医療サービスとなっています。
訪問看護という言葉の使い方
訪問看護は、医師の指示を受けた看護師や保健師が自宅を訪問し、医療処置や看護ケアを行う際に用いられる言葉です。
在宅医療を支える仕組みの一つであり、「病院に行かずに自宅で医療を受けられるサービス」という意味合いを持ちます。
例:訪問看護の使い方
-
退院後は訪問看護を利用して自宅で療養している。
-
訪問看護師が点滴やリハビリをしてくれるので安心だ。
-
在宅医療では訪問看護が重要な役割を果たしている。
訪問介護と訪問看護の違いとは
訪問介護と訪問看護の違いは、提供する内容、担当する専門職、対象となる人の状態にあります。
まず、提供内容の違いを整理すると、訪問介護は食事や入浴、掃除など日常生活を助けることが中心です。
一方、訪問看護は医療的なサポートであり、病状の観察や処置、服薬管理、リハビリなどを行います。
次に関わる専門職です。訪問介護は介護福祉士やホームヘルパーといった介護の専門職が対応します。
対して訪問看護は、必ず医療資格を持つ看護師や保健師が担当し、医師の指示に基づいてサービスを行います。
対象者の違いも重要です。
訪問介護は主に要介護・要支援と認定された高齢者が中心ですが、訪問看護は年齢を問わず、医療的なサポートを必要とする在宅療養者全般が対象になります。
つまり、似たような言葉でありながら、訪問介護は生活支援サービス、訪問看護は医療支援サービスという明確な役割分担があるのです。
両者を適切に使い分けることで、自宅で安心して暮らせる環境が整えられます。
まとめ
訪問介護と訪問看護の違いは、サービス内容・担当者・対象者にあります。
訪問介護は介護福祉士やヘルパーが生活全般を支えるサービスであり、訪問看護は看護師や保健師が医師の指示に基づき医療ケアを行うサービスです。
言葉が似ているため混同されやすいですが、両者は役割が大きく異なります。
利用者の状況に合わせて適切に選ぶことが、自宅での安心した暮らしにつながります。
さらに参考してください: