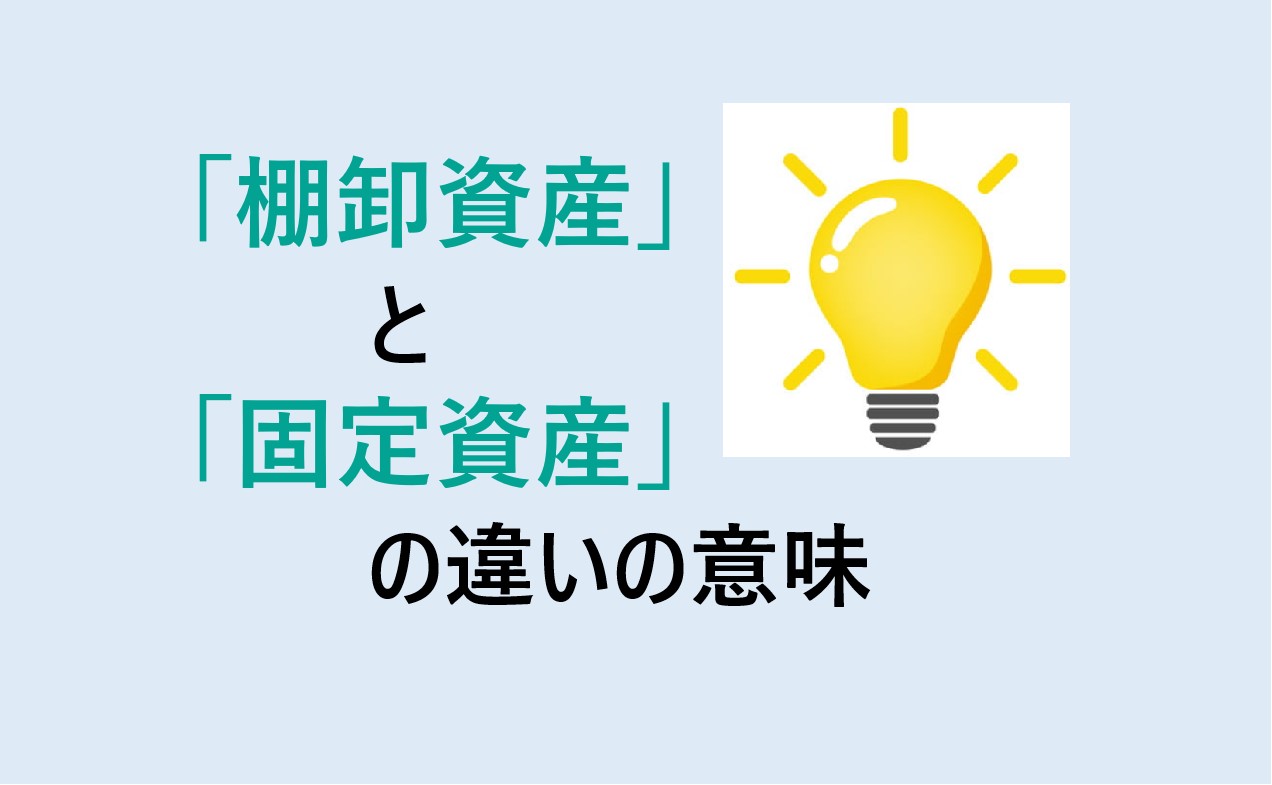会社の財務や会計の話をするときによく登場する言葉に「棚卸資産」と「固定資産」があります。
どちらも「資産」に分類されますが、それぞれの役割や目的は大きく異なります。
本記事では、棚卸資産と固定資産の違いについて、初心者でも理解できるようにやさしく解説します。
棚卸資産とは
棚卸資産(たなおろししさん)とは、「販売を目的として企業が保有する資産」、つまり在庫のことを指します。
会社が日々の営業活動の中で、顧客に提供するために所有している商品や製品、または製品を作るための原材料などがこれに含まれます。
例えば、食品を製造・販売している企業であれば、完成品の食品だけでなく、原材料の小麦粉や調味料、包装材などもすべて棚卸資産として扱われます。
また、新しい商品の試作品も含まれる点も特徴です。
企業では期末などに「棚卸し(在庫確認)」を行い、どれだけの在庫があるかをチェックしますが、この在庫全体が会計上では棚卸資産として処理されます。
販売が進めば在庫は減り利益につながりますが、売れ残れば不良在庫としてコスト増加のリスクにもなります。
棚卸資産という言葉の使い方
棚卸資産は、主に会計や財務管理の現場で使用され、企業の販売活動に直接関係する「流動資産」の一つとして扱われます。
例:
-
決算時に棚卸資産の金額を見直す必要がある。
-
売れ残った商品は棚卸資産として不良在庫扱いになる。
-
原材料も棚卸資産として分類される。
固定資産とは
固定資産(こていしさん)は、企業が事業を継続的に運営していくために、1年以上の長期間使用する目的で保有している資産のことです。
代表的なものとしては、建物、土地、機械設備、車両などがあり、これらは「有形固定資産」と呼ばれます。
一方で、ソフトウェアや商標権、特許などの目に見えない資産は「無形固定資産」として分類されます。
たとえば、製造業で使う大型機械や、オフィスで使用するパソコンやそのソフトウェアも固定資産に該当します。
これらの資産は、日々の販売には直接関係ありませんが、会社の生産性や運営の基盤となる重要な資源です。
固定資産という言葉の使い方
固定資産は、財務諸表や決算書で重要な項目として扱われ、減価償却の対象となることが一般的です。
長期的な視点での投資資産としても使われます。
例:
-
新工場の建設に伴い固定資産が増加した。
-
パソコンやソフトウェアも固定資産として管理されている。
-
毎年の決算で固定資産の減価償却を計上する。
棚卸資産と固定資産の違いとは
棚卸資産と固定資産の違いは、その用途と保有期間にあります。
まず、棚卸資産は「販売目的」で短期間保有される在庫などの資産を指します。
商品の売買や製品の製造・販売など、企業の営業活動に直接結びついた資産です。
一方、固定資産は「事業運営のため」に長期的に使用される資産であり、直接的に販売されることはありません。
オフィスの建物や製造機械のように、会社の運営を支えるために不可欠なものです。
さらに会計上の分類でも、棚卸資産は流動資産、固定資産は固定資産というように区別されます。
また、棚卸資産は売れることによって利益につながりますが、固定資産は減価償却によって徐々に価値が減っていくという特徴もあります。
このように、どちらも「資産」であることには変わりありませんが、性質や目的がまったく異なるため、企業の経営や会計を理解する上でこの違いをしっかり把握しておくことが大切です。
まとめ
棚卸資産と固定資産の違いをしっかり理解することで、企業の資産管理の基本が見えてきます。
棚卸資産は短期的に販売されることを目的とした在庫、固定資産は長期的に会社運営を支える設備やツール。
似ているようで全く異なるこの2つの資産を正しく使い分けることが、経営判断や財務分析に役立ちます。
さらに参照してください:内部留保と利益剰余金の違いの意味を分かりやすく解説!