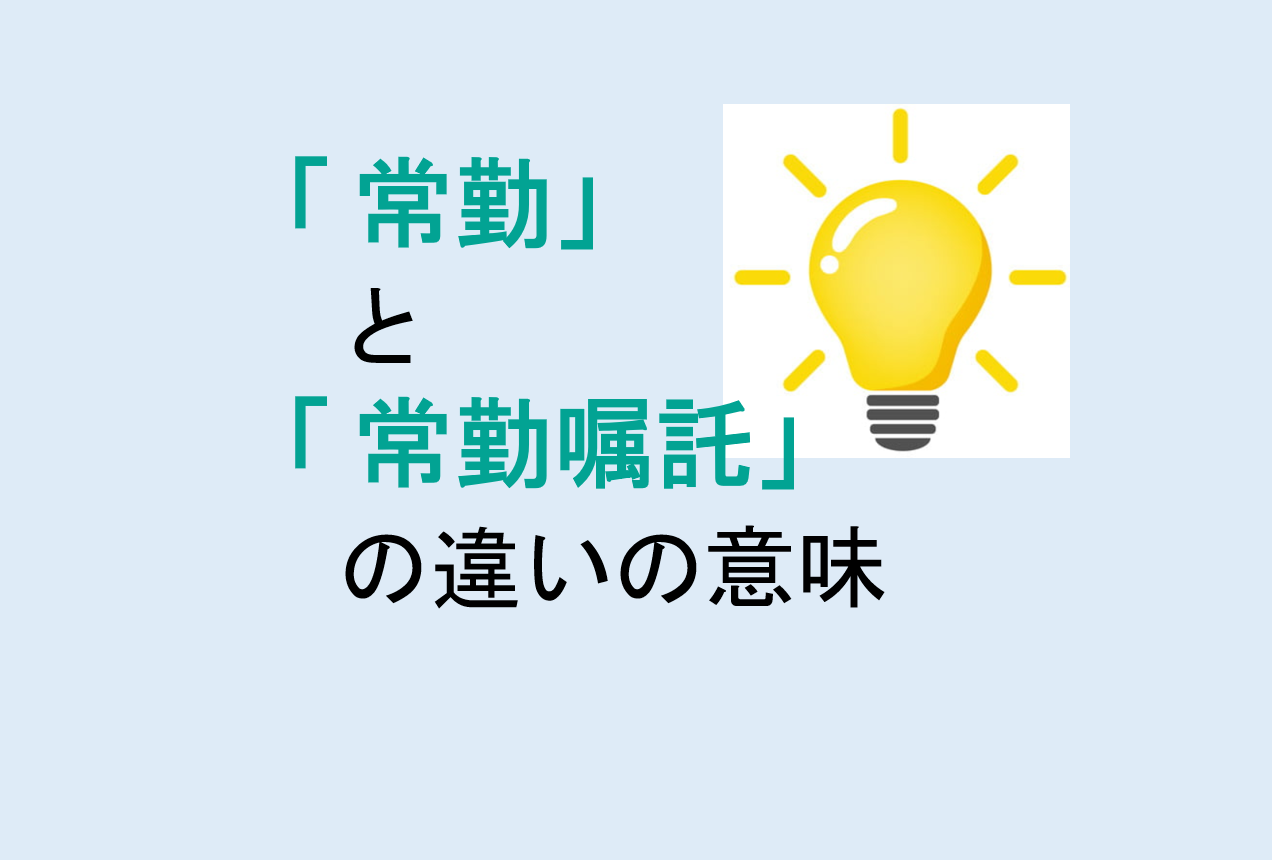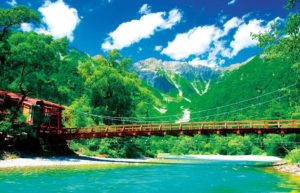働き方に関する言葉としてよく使われるのが常勤と常勤嘱託です。
どちらも「毎日一定の時間勤務する」という点で共通していますが、雇用形態や立場に違いがあります。
一般的に常勤は正社員を指し、安定した雇用契約のもとで勤務するのに対し、常勤嘱託は嘱託職員として契約を結び、毎日働きながらも正社員とは異なる位置づけになります。
この記事では、常勤と常勤嘱託の違いを分かりやすく解説し、それぞれの意味や使い方を具体例とともに紹介します。
常勤とは
常勤とは、臨時ではなく、原則として毎日一定の時間勤務することを指します。
多くの場合、週5日・1日8時間程度の勤務を行い、フルタイムで働く人がこれに該当します。
企業や組織において、主力となる人材として働くスタイルが常勤です。
一般的に常勤の従業員は正社員として雇用され、社会保険や福利厚生が整っているケースが多く、長期的なキャリア形成を前提としています。
また、職場において責任ある役割を担うことも多く、組織の中核として期待される存在です。
医療機関や大学などでも「常勤医」「常勤講師」といった表現が使われるように、フルタイムで働く専門職を表す際にも利用されます。
このように、常勤は「組織に毎日所属し、安定的に勤務する人」を意味する言葉です。
常勤という言葉の使い方
常勤は、日常的にその場に勤務していることを強調する際に使われます。
例:常勤の使い方
-
弊社には常勤の社員が常に対応しているので、休日でも連絡が可能です。
-
病院では常勤医が複数在籍しているため、診察体制が整っている。
-
大学には研究専任の常勤講師が配置されている。
常勤嘱託とは
常勤嘱託とは、正式な正社員としてではなく嘱託契約によって雇用され、毎日一定時間勤務する人を指します。
嘱託とは、会社や組織と期間を定めた契約を結び、その契約内容に基づいて働くスタイルです。
定年退職後の再雇用や、特定の専門知識やスキルを持つ人材を活用する場合によく用いられる働き方です。
勤務日数や時間は常勤と同じであっても、雇用上は正社員とは区別され、給与体系や福利厚生が異なるケースがあります。
そのため、常勤嘱託は「フルタイム勤務だが非正規雇用」という特徴を持っています。
組織にとっては経験豊富な人材を柔軟に確保できる仕組みであり、労働者にとってはライフスタイルに合わせた働き方を選べる点にメリットがあります。
常勤嘱託という言葉の使い方
常勤嘱託は、定年後の再雇用や特別な契約で勤務しているケースでよく使われます。
例:常勤嘱託の使い方
-
定年退職後、5年間は常勤嘱託として再雇用されることになった。
-
会社に専門的な知識を提供するため、常勤嘱託の契約を結んだ。
-
常勤嘱託として勤務しているが、正社員時代より責任が軽くなった。
常勤と常勤嘱託の違いとは
常勤と常勤嘱託の違いは、雇用形態と立場にあります。
まず、常勤は正社員として雇用されることが多く、安定した雇用関係のもとでフルタイム勤務を行います。
社会保険や福利厚生が充実している場合が多く、キャリア形成や昇進の機会も確保されています。
一方、常勤嘱託は「嘱託契約」に基づいて雇用されるため、フルタイムで勤務していても正社員とは扱いが異なります。
給与体系や契約期間に制限がある場合が多く、雇用の安定性は正社員より低いこともあります。
しかし、経験豊富な人材を定年後も活用できる制度として、近年は幅広い企業で導入されています。
両者の違いを整理すると、常勤は「正社員としてフルタイム勤務する人」、**常勤嘱託は「嘱託契約でフルタイム勤務する人」**という点に集約されます。
勤務日数や時間は同じでも、雇用形態と待遇に差があることを理解しておくことが重要です。
まとめ
常勤と常勤嘱託の違いは、勤務時間ではなく雇用形態にあります。
常勤は正社員としてフルタイム勤務する人を指し、雇用の安定性や福利厚生が整っています。
一方、常勤嘱託は嘱託契約を結び、毎日勤務しながらも正社員とは異なる立場にある働き方です。
両者の違いを理解することで、自分に合った働き方を選びやすくなり、キャリアプランの参考にもなるでしょう。
さらに参考してください: