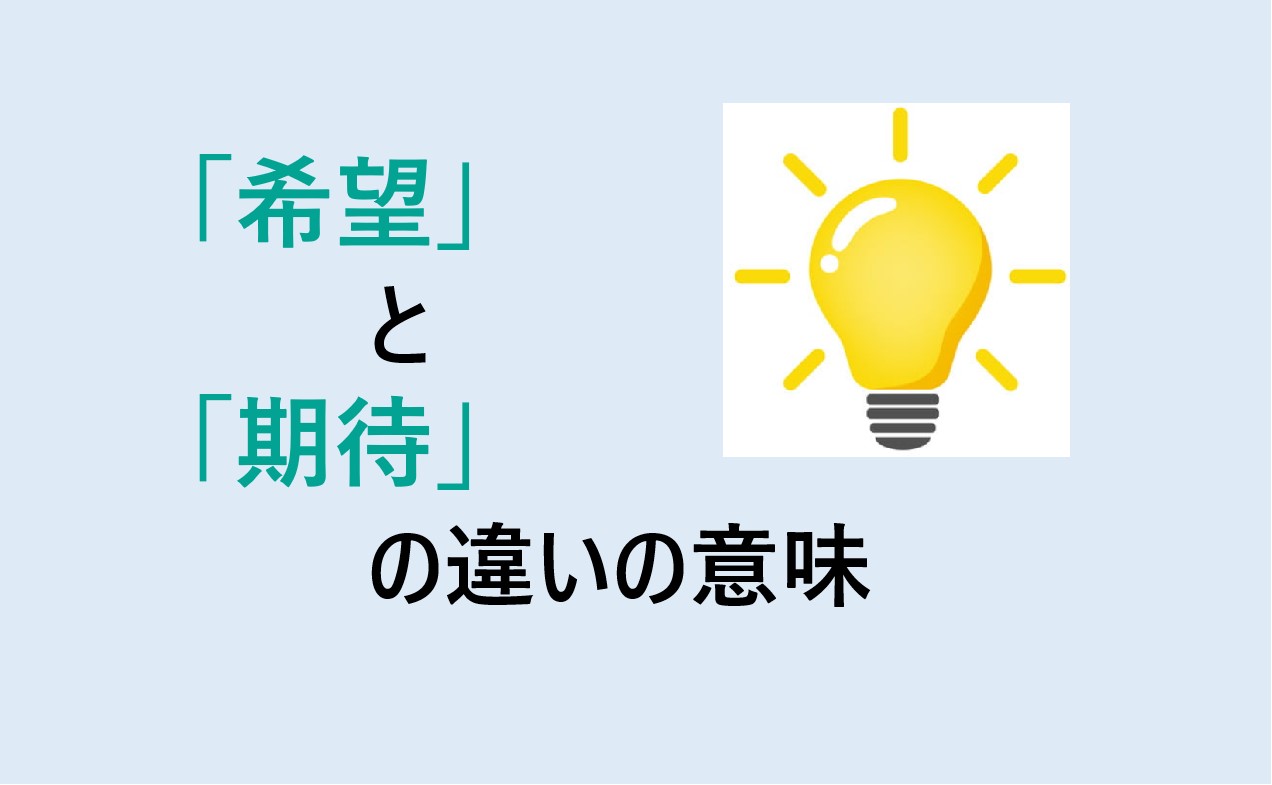日常生活やビジネスの場面でよく耳にする「希望」と「期待」という言葉。
どちらも「こうなってほしい」という思いを表す際に使われますが、そのニュアンスや使い方には明確な違いがあります。
この記事では、「希望と期待の違い」について丁寧に解説し、それぞれの言葉を正しく使い分けるためのポイントをご紹介します。
希望とは
希望(きぼう)とは、「あることが実現してほしいと強く願うこと」を意味します。
未来に対する前向きなイメージや、自分の意思に基づいた願望が含まれており、「こうなってほしい」という理想の状態を思い描くことです。
また、自分自身がその願いを叶えるために努力や行動を起こす場合も多く、主体的な思いが強いのが特徴です。
加えて、「希望」には「明るい未来への見通し」という意味もあります。
この場合は、必ずしも明確な目標があるわけではなく、「きっと良いことがあるだろう」という楽観的なイメージに近い意味合いになります。
希望という言葉の使い方
希望は、「こうなってほしい」と願う気持ちを表すときに使われます。
自分の中から湧き上がる思いや夢に対して使われることが多く、状況に応じて「希望する」「希望を持つ」などの形で使用されます。
例:
-
希望通りの企業に就職できた。
-
将来は海外で暮らしたいという希望がある。
-
最後まで希望を捨てずに努力し続けた。
期待とは
期待(きたい)とは、「何かが起きることを望みながら待つこと」を指します。
自分の意思というよりも、相手や環境が変化することで、自分にとって良い結果が得られることを待ち望むニュアンスが強く、受け身的な感覚が含まれています。
また、「期待」には対象が人物である場合も多く、その人物の能力や役割に対して「良い結果を出してくれるだろう」と予想し、それに対する希望を持つという意味も含まれます。
そのため、相手にプレッシャーを与える表現としても使われることがあります。
期待という言葉の使い方
期待は、他者や未来の出来事に対して「良い結果になるだろう」と見込む気持ちを表すときに使われます。
「期待する」「期待を寄せる」「期待に応える」などの形でよく使われます。
例:
-
新しいプロジェクトの成功に期待している。
-
今回は期待に応えられなかった。
-
その映画にはかなり期待していたが、少しがっかりした。
希望と期待の違いとは
希望と期待の違いを明確にするには、それぞれの「願い方」と「心の向け方」に注目する必要があります。
希望は、主に自分の内面から湧き出る「こうなってほしい」という積極的な願望です。
そして、自分の行動によって実現しようとする意思が含まれています。
つまり、主体的で能動的な気持ちです。
一方、期待は、他人や状況に対して「こうなってくれたらいいな」と思いながら待つ気持ちを表します。
自分から行動するわけではなく、何かが起きるのを受動的に待つという性質を持っています。
また、対象に対して「きっとそうなるはず」とある程度の確信を持っている点も特徴です。
簡単に言えば、希望は「自分が未来に向けて願い、動く」気持ち、期待は「他人や環境に何かを望み、待つ」気持ちです。
どちらも未来への前向きな感情ではありますが、視点と主語が異なる点が大きな違いです。
まとめ
今回は、「希望と期待の違い」について詳しく解説しました。
希望は「自分が願い行動する主体的な気持ち」、期待は「他者や環境に望みをかけて待つ受動的な気持ち」です。
それぞれの使い分けを理解することで、より正確で自然な表現ができるようになります。
ぜひ日常会話や文章作成に役立ててみてください。
さらに参照してください:興味と関心の違いの意味を分かりやすく解説!