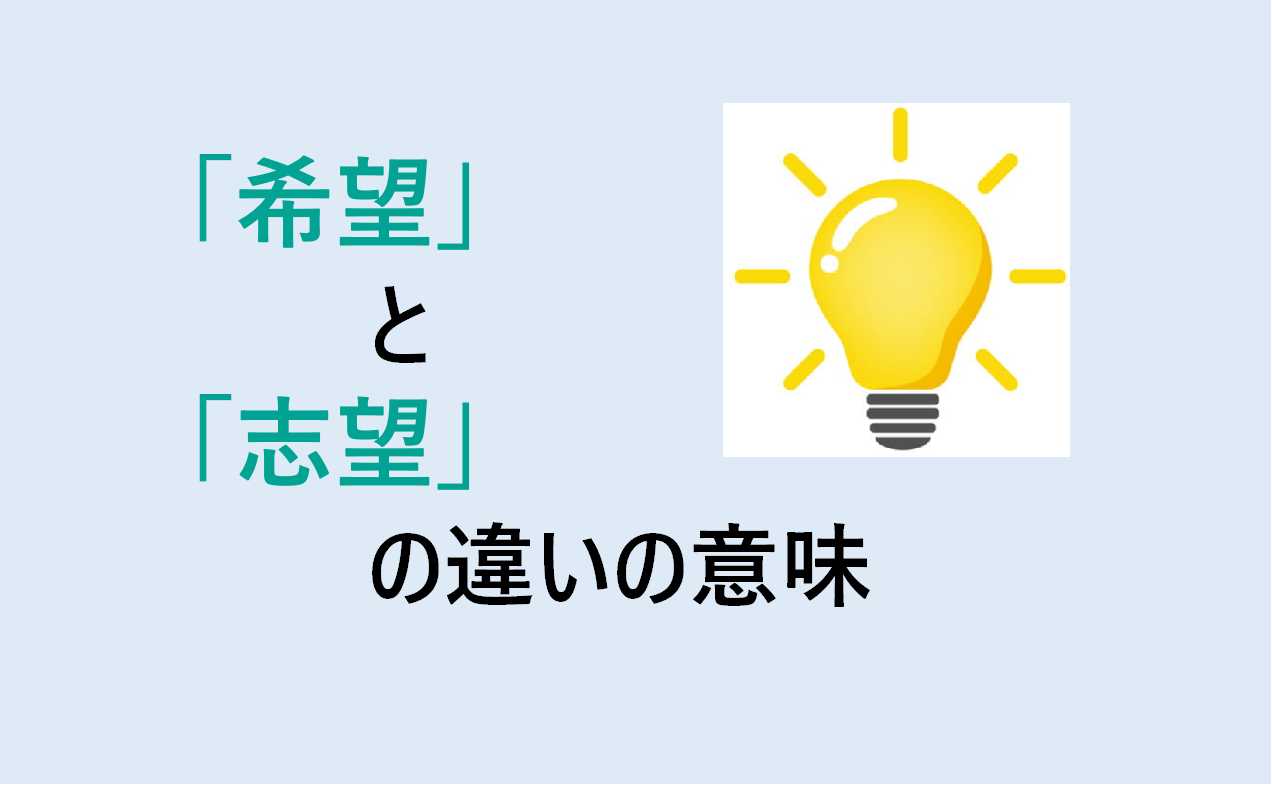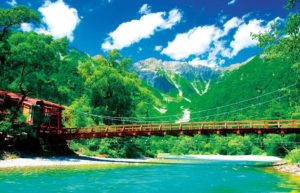「希望」と「志望」はどちらも「望む」という意味を持つ言葉ですが、実際に使う場面やニュアンスに違いがあります。
この違いをしっかり理解して使い分けることで、より適切な表現が可能になります。
本記事では、「希望」と「志望」の意味や使い方を徹底的に解説し、実際の例文も交えて、どのように使い分けるかを紹介します。
希望とは
「希望(きぼう)」は、ある事柄が実現することを望むことや、将来に対する期待の気持ちを指します。
つまり、現実に起こるであろうと予測する未来に対して、良い結果を期待して願うことです。
例えば、「大学に合格したい」「健康が保たれるように祈る」といった、実現を望む具体的な事柄を指す場合に使われます。
また、「希望」には明るい見通しという意味も含まれており、ポジティブな期待を表す際に使われることが多いです。
たとえば、復興の希望の光など、未来に対して期待を込めた言葉として使用されます。
希望という言葉の使い方
「希望」は、将来に対する明るい見通しや実現を願う気持ちを表す際に使われます。
自分自身が望んでいることに限らず、他者のために願う場合にも使います。
例:
-
「希望に満ちた未来を信じる」
-
「A大学に入学することを希望する」
-
「復興に向けた希望の光が見えてきた」
志望とは
「志望(しぼう)」は、自分自身が「こうなりたい」「こうしたい」と強く願う気持ちを表現する言葉です。
特に職業や進路、目標に対する意欲や強い願望を指します。
「志望」は、自分の未来について明確な目標を持って、その実現を強く望む場合に使用されます。
例えば、「作家になりたい」「医師になりたい」といった、自己の目標に対する強い希望を表します。
「志望」は自分の意志に関わることで、他人のために使用することはありません。
自分が望む将来に対して強い意思を持っていることが特徴です。
志望という言葉の使い方
「志望」は、特に自分自身の目標や職業、進路に対して使用される言葉です。
これは自分の意思が強く反映されたものなので、他人に対して使うことはありません。
例:
-
「志望する職業に就く」
-
「医師を志望して勉強を頑張る」
-
「第一志望の大学に合格することが目標」
希望と志望の違いとは
「希望」と「志望」は、一見似ているように感じますが、微妙な違いがあります。
両者は「望む」という意味を持ちますが、使われる状況やニュアンスが異なります。
まず、「希望」は、将来の事柄が実現することを期待して望むことを指します。
この意味では、自分以外のものについても使うことができます。
たとえば、「新薬が患者に希望を与えた」といった場合、他者のために「希望」を表現しています。
一方で、「志望」は、自己の目標や理想に対して強く望む気持ちを表現します。
これは自分自身の意志に関連するもので、他者に対して使うことはありません。
例えば、「私は作家を志望している」といった場合、他人ではなく自分自身が持つ目標に焦点を当てています。
また、「希望」には、未来に対する期待や明るい見通しを含む場合があり、「希望を持つ」「希望の光」といった表現が使われますが、「志望」にはそのような明るい見通しの意味はありません。
したがって、「復興を志望する」という表現は不自然で、「復興の希望を持つ」といった表現が適切です。
まとめ
「希望」と「志望」はどちらも「望む」という意味を持っていますが、その使用シーンには大きな違いがあります。
-
「希望」は、将来の実現を願うことや、明るい未来への期待を表し、自分以外の事柄にも使うことができます。
-
一方、「志望」は、自己の目標に対して強い意志を持って望むことを表現し、自分のことに関してのみ使われます。
この違いを理解し、適切に使い分けることで、より豊かな表現が可能になります。
さらに参照してください:見通しと見込みの違いの意味を分かりやすく解説!