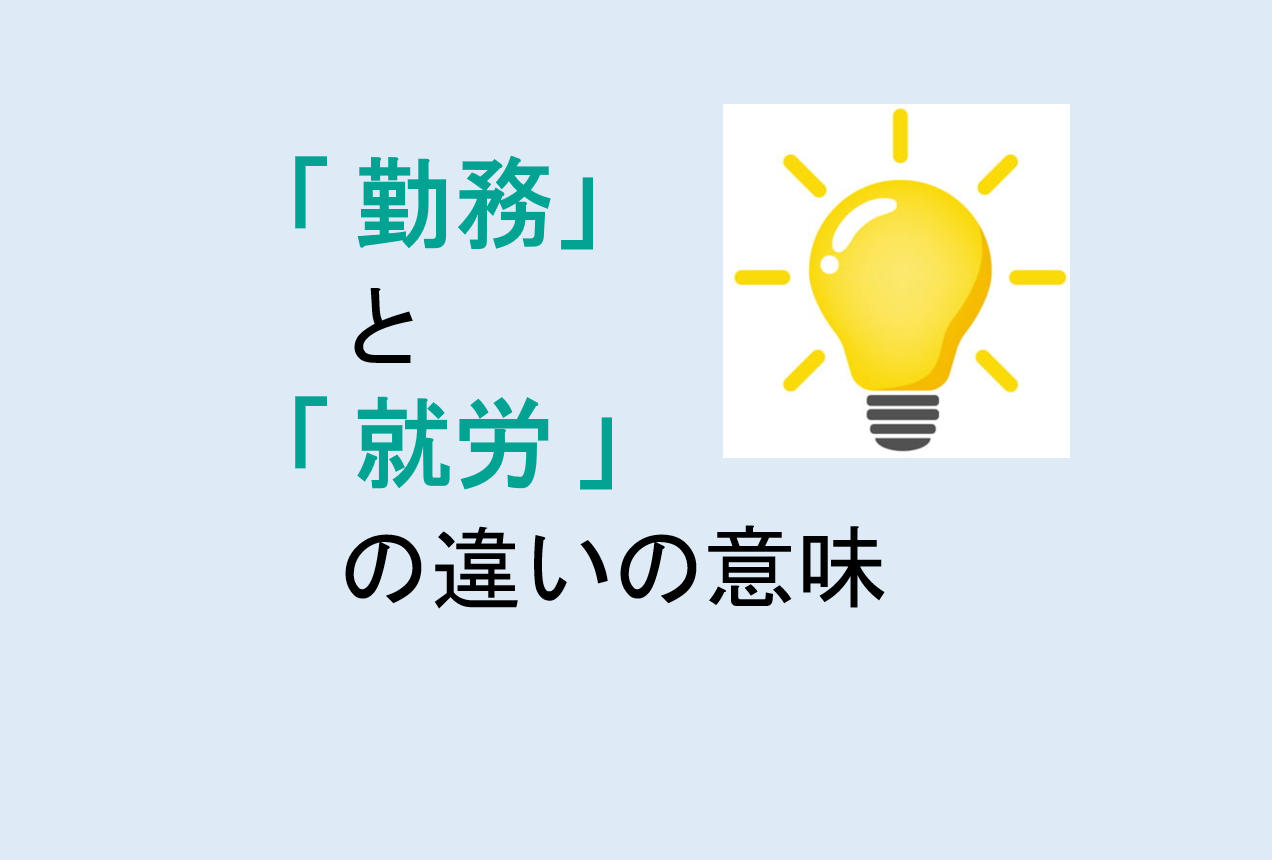社会人として働いていると、勤務や就労という言葉を耳にする機会が多くあります。
どちらも「仕事をすること」に関わる言葉ですが、実は意味や使い方には違いがあります。
勤務は会社や官庁などの勤め先に出向いて働くことを指し、就労は仕事に就くことや実際に働き始めることを意味します。
これらを混同すると、文章や会話の中で誤解を招く可能性もあります。
本記事では、勤務と就労の違いを詳しく解説し、それぞれの意味や使い方を理解しやすいように具体例を交えてご紹介します。
勤務とは
勤務とは、会社や官庁といった勤め先に出向き、そこで仕事をすることを意味します。
多くのビジネスパーソンは毎日電車や車を利用して会社へ向かい、到着後に与えられた業務を遂行します。
これが一般的に言う勤務です。
重要なポイントは、「勤め先に出かけて働くこと」が含まれる点です。
そのため、自営業やフリーランスのように特定の勤め先がなく、自宅や外出先で自由に仕事をする場合には、勤務という言葉は通常使いません。
ただし、企業に雇用されている人が会社の都合で在宅勤務をする場合には「自宅勤務」と表現されます。
これはあくまで「勤め先がある状態で働き方が自宅になっている」という意味です。
このように、勤務は「どこで働くのか」という場所に重点が置かれた言葉であり、組織に所属している人に対してよく使われる表現です。
勤務という言葉の使い方
勤務は「勤め先に出向いて働くこと」を表す場面で用いられます。
特定の会社や役所に所属し、決まった場所に通って働くことが前提です。
逆に、仕事そのものには従事していても、勤め先に通う必要がない自営業者やフリーランスには通常使われません。
勤務の使い方の例
-
勤務中に私用の電話を控えてください。
-
長年、同じ企業に勤務している。
-
彼は来月から新しい会社に勤務する予定だ。
就労とは
就労とは、仕事に就くこと、仕事を始めること、または実際に働いている状態を指します。
アルバイトや正社員といった雇用形態にかかわらず、生活費を得るために働く行為すべてが就労にあたります。
就労の大きな特徴は、「勤め先に通う」という意味が含まれていない点です。
たとえば専業主婦(主夫)がパートを始める場合や、学生が就職活動を経て初めて働き始める場合、これらはいずれも就労と表現されます。
また、就労は単に「仕事に就いた」という状態を示すだけでなく、「働き始めること」そのものを含むため、就職直後の人や短時間の労働も含める幅広い概念です。
さらに「市が就労を支援する」といった表現では、社会的なサポートや政策的な文脈でもよく用いられます。
就労という言葉の使い方
就労は「仕事に就く」「働き始める」という意味合いで使われ、勤め先の有無や働く場所は問いません。
社会政策や労働支援の文脈でも頻繁に用いられる言葉です。
就労の使い方の例
-
市が若者の就労を支援している。
-
海外で就労することを目指して語学を学んでいる。
-
定年後も就労を続けたいと考える人が多い。
勤務と就労の違いとは
勤務と就労はどちらも「働くこと」に関わる言葉ですが、対象とする範囲やニュアンスが異なります。
まず勤務は、会社や官庁など「勤め先があること」が前提です。
そのうえで、出勤し実際に働く行為を指します。
したがって、勤務という言葉を使う場合には、働く人が組織に所属しており、仕事をする場所へ通うことが含まれます。
一方、就労はより広い意味を持ちます。
就職して働き始めること、あるいは働いている状態全般を表し、必ずしも勤め先へ出向くことを前提としていません。
アルバイトやパート、フリーランスといった働き方も含めて使われる言葉です。
また行政や福祉の分野では、就労支援や就労機会といった形で社会的な取り組みを表す言葉としても広く使用されています。
具体例を挙げると、専業主婦がパートを始める場合「就労」とはいえますが、「勤務」とは表現しません。
なぜなら、勤務は「勤め先に出向く」ニュアンスを伴うためです。
逆に会社員が出社して働く場合には「勤務」という言葉が自然に使われますが、この場合でも広義には「就労している」と表現できます。
つまり、勤務は場所や組織に重きを置いた表現、就労は仕事に就くという状態そのものに焦点を当てた表現だと整理できます。
この違いを理解することで、状況に応じた適切な言葉を選ぶことができます。
まとめ
勤務は勤め先に出向いて仕事をすることを意味し、就労は仕事に就き、実際に働き始めることを指します。
勤務は「勤め先」という場所の要素を含むのに対し、就労は働く状態全般を幅広く表す点が大きな違いです。就職活動や労働政策などの文脈でも使い分けられるため、この違いを理解しておくことで、文章や会話の表現がより正確になります。
さらに参考してください: