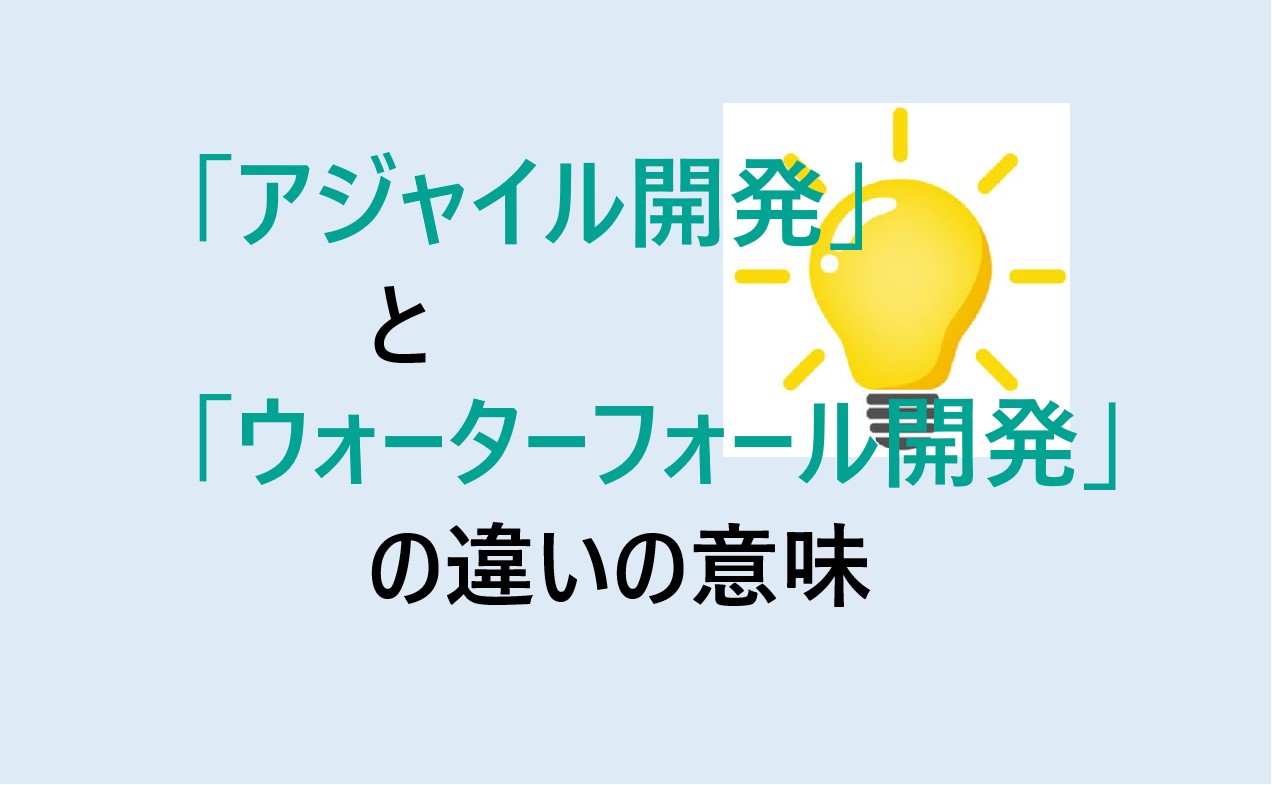ソフトウェア開発の現場でよく耳にする「アジャイル開発」と「ウォーターフォール開発」。
どちらもアプリケーション開発の手法として知られていますが、その進め方や考え方には大きな違いがあります。
この記事では、初心者にもわかりやすく、アジャイル開発とウォーターフォール開発の違いについて詳しく解説していきます。
アジャイル開発とは
アジャイル開発とは、ソフトウェア開発の手法の一つで、開発工程を「イテレーション」と呼ばれる小さな単位に分割し、それぞれの単位で設計・開発・テスト・リリースまでを繰り返すスタイルです。
「Agile(アジャイル)」は英語で「素早い」「俊敏な」という意味を持ち、その名の通り、迅速な開発と柔軟な対応を重視しています。
この手法では、要件の変更にも対応しやすく、ユーザーのフィードバックをもとに素早く機能の改善や追加が行える点が大きな特徴です。
一方で、全体像の把握が難しくなりやすく、統一感のある設計が求められる大規模開発では課題となる場合もあります。
アジャイル開発という言葉の使い方
アジャイル開発は、短期間でリリースを重ねていく開発プロジェクトや、変化の激しい業界で重宝されます。
チーム間のコミュニケーションが密な開発体制でよく用いられます。
例:
-
スタートアップではアジャイル開発が主流になっている。
-
顧客の要望に素早く対応するためにアジャイル開発を採用した。
-
スプリントごとに改善を繰り返すのがアジャイル開発の強みだ。
ウォーターフォール開発とは
ウォーターフォール開発とは、ソフトウェア開発の伝統的な手法で、開発工程を上流から下流へと一方向に進めていくスタイルです。
設計、プログラミング、テスト、リリースという各工程を順番に、段階ごとに完了させていきます。
この開発手法は、まるで滝(Waterfall)が上から下へと流れるように、一度進んだ工程には基本的に戻らないのが特徴です。
全体設計を最初に固めてから進めるため、計画通りにプロジェクトを進行しやすい反面、途中での仕様変更には対応しづらいという短所があります。
ウォーターフォール開発という言葉の使い方
ウォーターフォール開発は、大規模な業務システムの開発など、要件が事前に明確に決まっているプロジェクトで多く用いられます。
品質保証が重視される場面にも向いています。
例:
-
官公庁向けのシステム開発ではウォーターフォール開発が選ばれることが多い。
-
長期計画が必要な案件ではウォーターフォール開発の方が安心感がある。
-
設計段階でしっかり詰めるのがウォーターフォール開発のポイント。
アジャイル開発とウォーターフォール開発の違いとは
アジャイル開発とウォーターフォール開発の違いは、開発の進め方そのものにあります。
ウォーターフォール開発は、計画からリリースまでを段階的に順を追って進める直線的な方法であり、途中での変更が難しいのが特徴です。
一方、アジャイル開発は、計画を小さな単位に分け、短期間のサイクルで反復的に開発を行うことで、柔軟な対応が可能です。
アジャイル開発では、ユーザーの声を反映したり、トレンドの変化に素早く対応できるため、Webサービスやスマホアプリの開発に適しています。
対してウォーターフォール開発は、厳格な品質管理が必要な大規模プロジェクトや、途中での仕様変更が許されない開発に向いています。
近年では、これら2つの手法を組み合わせた「ハイブリッド型」も増えており、要件定義はウォーターフォールで行い、開発部分はアジャイルで進めるなど、柔軟なアプローチが主流となりつつあります。
まとめ
アジャイル開発とウォーターフォール開発の違いは、開発スタイルの柔軟性やスピード感にあります。
状況に応じて適切な手法を選ぶことが成功の鍵です。
最近では一方に偏らず、両方のメリットを活かす開発スタイルが支持されています。
さらに参照してください:ハードウェアとソフトウェアの違いの意味を分かりやすく解説!