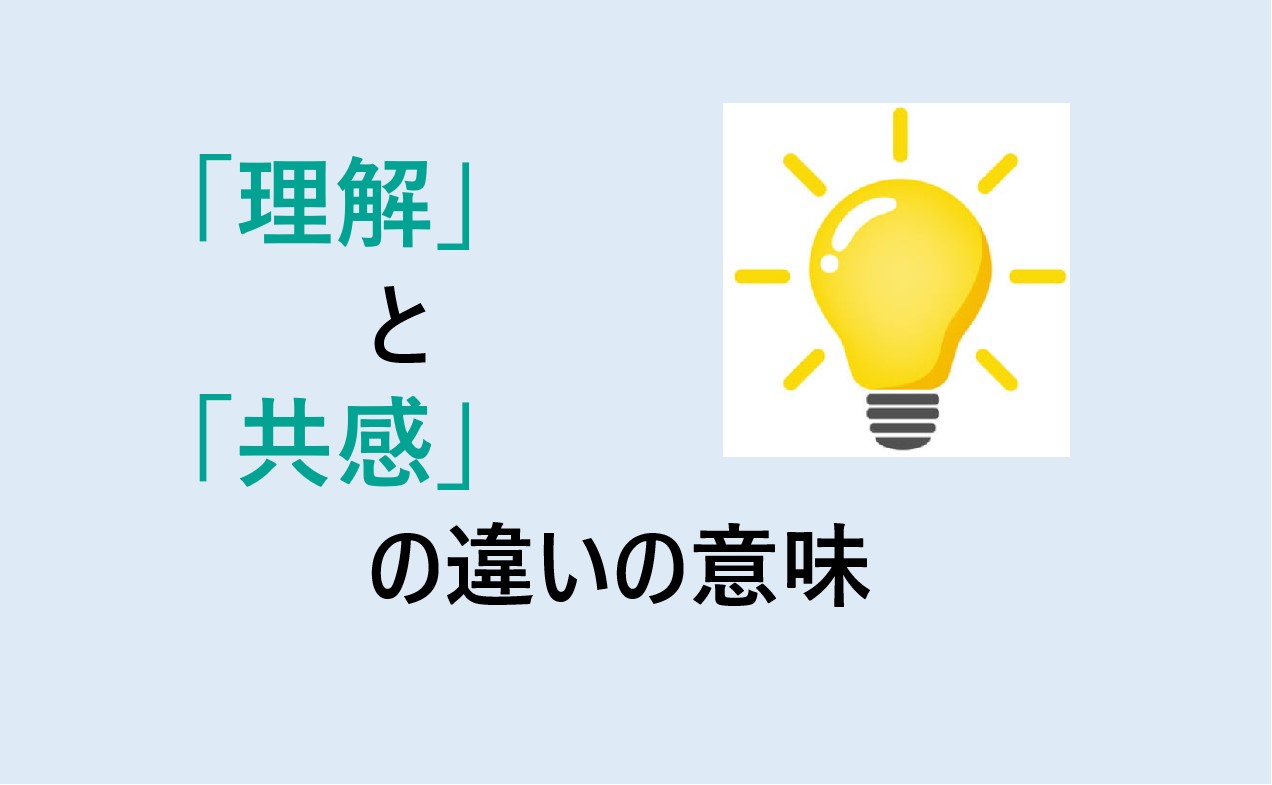日常生活や人間関係において頻繁に使われる「理解」と「共感」。
この2つの言葉は似ているようで、その意味や使い方には明確な違いがあります。
本記事では、理解と共感の違いをわかりやすく解説し、実例を交えてその違いを明確にします。
理解とは
理解とは、物事の意味や構造を筋道立てて正確に把握することを指します。
また、他人の立場や気持ちを論理的に推し量ることも含まれます。
つまり、感情的というよりも、思考を通じて物事を「わかる」状態を意味しています。
例えば、料理用語の「ナッペ」や「8分立て」の意味を知り、それをどう実行するかがわかる状態は「理解」です。
また、同僚が風邪で会社を休んだと聞いて、「辛かったのだろう」と頭で見当をつけることも理解に当たります。
理解には以下の2つの意味があります:
-
情報や知識を筋道立てて正しく把握すること
-
他人の感情や状況を頭で判断し、推測すること
理解という言葉の使い方
理解は、学習内容や説明、または人の気持ちや考え方を「頭で把握する」ときに使われます。
ビジネスや教育現場でもよく登場する言葉です。
例:
-
『先生の話が難しくて理解できなかった』
-
『あの行動の理由を理解しようとしている』
-
『説明書を何度読んでも理解できない』
共感とは
共感とは、他人の感情や意見に対して「自分も同じように感じる」と思える状態を指します。
これは単に「わかる」だけでなく、「そうだよね」と心から思える、いわば感情レベルでの共有です。
たとえば、誰かが「熱が出て会社を休んだ」と話したとき、自分自身も「それは仕方ないよね」と思える場合、それは共感になります。
理解が頭で考える行為なら、共感は心で感じる行為です。
また、共感には「相手の視点で物事を見る」「相手の心で感じる」といった深い意味合いも含まれています。
共感という言葉の使い方
共感は、他人の意見や感情に「その通りだ」と感情的に同意する場合に使われます。
SNSやドラマ、対話の中で非常によく使われる言葉です。
例:
-
『その意見にとても共感しました』
-
『ドラマの登場人物の気持ちに共感できる』
-
『彼女の考え方にはどうしても共感できない』
理解と共感の違いとは
理解と共感の違いは、「頭でわかるか」「心で感じるか」という点にあります。
理解は、相手の感情や状況を論理的に分析し、「そういう考えもあるのか」と把握することです。
しかし、必ずしもその意見や感情に同意するとは限りません。
一方で、共感は「自分も同じ気持ちになれる」と感情的に共有している状態です。
たとえば、誰かが「長時間働いて疲れた」と言ったとき、「それは大変だったね」と感じるのが共感であり、「忙しかったんだろうな」と思考的に判断するのは理解です。
つまり、理解と共感の違いは次の通りです:
-
理解:頭でわかる。相手の気持ちを「推し量る」こと。
-
共感:心で感じる。相手の気持ちを「共有する」こと。
この違いを把握して使い分けることで、より深いコミュニケーションが可能になります。
まとめ
「理解」は論理的に「わかる」こと、「共感」は感情的に「感じる」ことです。
似ているようで違うこの2つの言葉を正しく使い分けることは、人間関係を築く上でも非常に重要です。
理解と共感の違いをしっかりと意識して、相手との距離感を適切に取るようにしましょう。
さらに参照してください;理解と納得の違いの意味を分かりやすく解説!