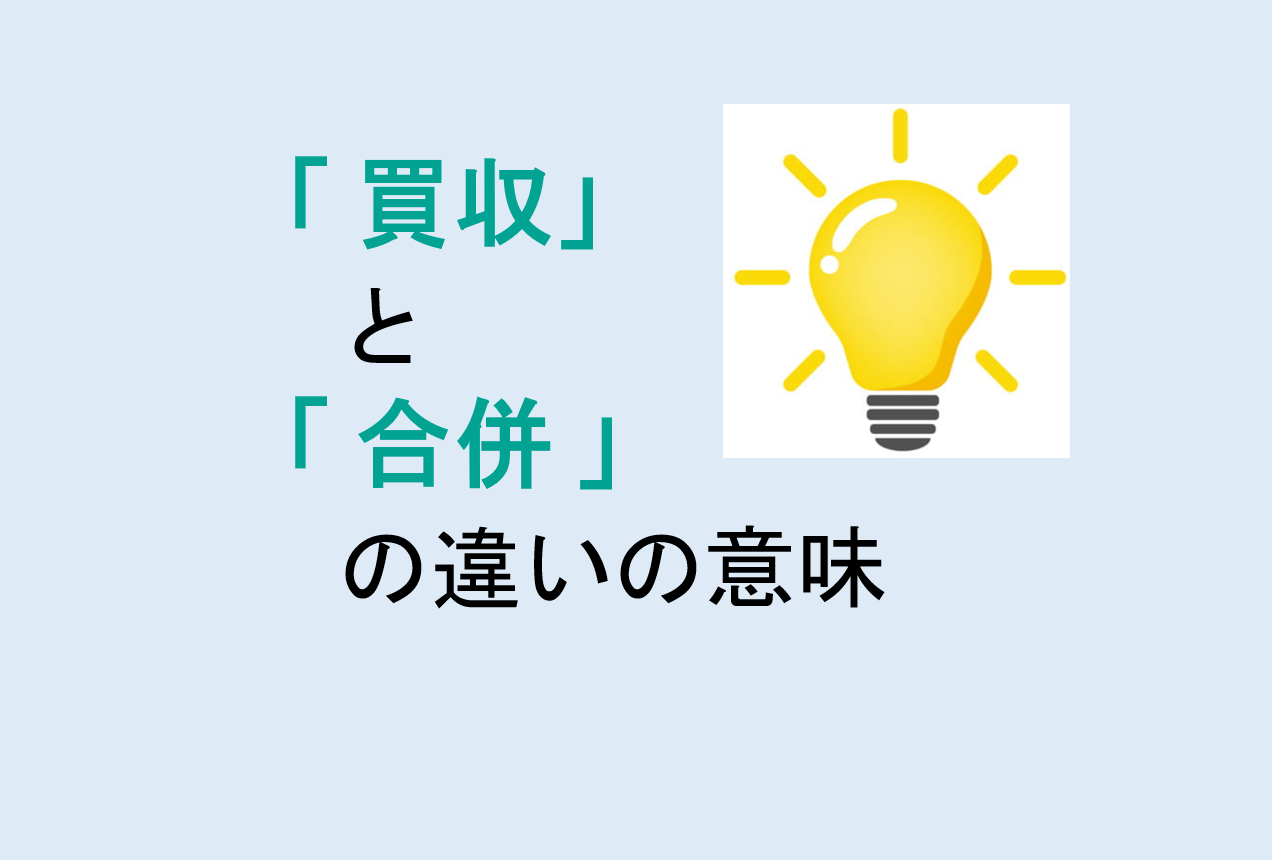企業戦略において頻繁に登場する言葉が買収と合併です。
どちらもM&A(Mergers and Acquisitions)の手法を指しますが、その意味や仕組みには大きな違いがあります。
買収は主に企業の経営権を取得することを目的とし、合併は複数の会社を一つにまとめることを意味します。これらは似ているようで、使い方やメリット・デメリットが異なり、経営判断に大きな影響を及ぼします。
本記事では、買収と合併の違いを分かりやすく解説し、それぞれの使い方や具体例も紹介します。
買収とは
買収とは、ある企業が他の企業の株式や事業を取得し、その経営権を握る行為を指します。
M&Aにおける「A(Acquisitions)」に相当し、典型的には対象企業の発行済株式の過半数を取得することで経営権を得ます。
方法としてはTOB(株式公開買付け)などが用いられ、敵対的に進められる場合もあります。
また、買収は企業全体を対象にするだけではなく、特定の事業部門だけを買い取ることも可能です。
これにより、自社の弱みを補強したり、強みを強化する戦略として活用されます。
資金と機会が合致すれば短期間で事業拡大を実現できるのが大きな特徴です。
ただし、買収後に思うようなシナジー効果が得られず、コストだけが増えるリスクも存在します。
そのため、明確な戦略を持って実行する必要があります。
買収という言葉の使い方
買収は、企業経営における戦略的な手段として使われます。
一般的には「株式の取得によって他社を支配すること」を意味しますが、「特定の事業部門を買い取ること」にも用いられます。
敵対的に行われるケースや、友好的に合意して進められるケースもあり、文脈に応じてニュアンスが変化します。
例:買収の使い方
-
不祥事による株価下落を機に、大手企業を買収するチャンスが訪れた。
-
豊富な資金力を持つ外資企業による買収が、国内市場に影響を与えている。
-
特定の技術を持つ事業部門だけを買収し、自社の競争力を高めた。
合併とは
合併とは、二つ以上の企業を一つにまとめて新しい組織体を作る、または一方の会社に他方を吸収させる経営行為です。
M&Aにおける「M(Mergers)」に該当し、大きく「吸収合併」と「新設合併」の二種類があります。
吸収合併では存続会社が消滅会社を取り込み、消滅会社の社名は消えるのが一般的です。
一方、新設合併は複数の会社を同時に解散させ、新しい会社を設立します。
日本では手続きが比較的簡便な吸収合併が主流です。
合併の目的は、経営の効率化や意思決定の迅速化、競争力の強化です。
同業同士の合併によって過当競争を避けたり、規模の経済を実現したりするメリットがあります。
しかし、統合後に経営方針や企業文化が合わず、かえって経営効率が低下するリスクもある点に注意が必要です。
合併という言葉の使い方
合併は「複数の企業を一つにまとめること」を指して使われます。
大きな企業が小規模企業を吸収する場合や、複数の会社が対等の立場で新会社を設立する場合に用いられます。
市場競争への対応や業界再編の一環としてよく用いられる用語です。
例:合併の使い方
-
地方銀行同士が経営基盤を強化するために合併を決定した。
-
業界再編の流れを受け、複数の企業が対等な条件で合併することになった。
-
激しい競争環境の中で生き残るために、企業は合併を選択するケースが増えている。
買収と合併の違いとは
買収と合併の違いは、その仕組みと結果にあります。
買収は株式や事業の取得によって経営権を手に入れる方法で、買収された企業は社名や組織が残ることもあります。
対して合併は複数の企業を一つにまとめる方法であり、消滅会社の社名は基本的に残りません。
また、戦略的な意味も異なります。
買収は短期的に特定の事業や経営権を獲得できるため、迅速な事業拡大や弱点補強に有効です。
一方で、シナジーが期待通りに発揮されなければ、投資が無駄になる可能性があります。
一方、合併は企業同士が一体化することで効率化やスケールメリットを得られますが、異なる企業文化や経営体制を融合させる難しさが課題です。
さらに、一度合併してしまうと元に戻るのは困難で、経営判断を誤ると競争力低下につながるリスクもあります。
要するに、買収は「相手を取り込みながら自社の戦略に合わせる方法」であり、合併は「企業同士が一つになって新たな組織を形成する方法」と言えるでしょう。
目的や状況に応じて選択される手段であり、企業の成長戦略において重要な位置を占めています。
まとめ
買収と合併の違いを整理すると、買収は株式や事業の取得を通じて他社の経営権を獲得する方法であり、合併は複数の企業を一つに統合する方法です。
それぞれにメリットとデメリットが存在し、企業の成長や競争力強化に大きな影響を与えます。
この記事を参考に、M&Aの場面で使われるこれらの用語の正しい意味と違いを理解しておきましょう。
さらに参考してください: