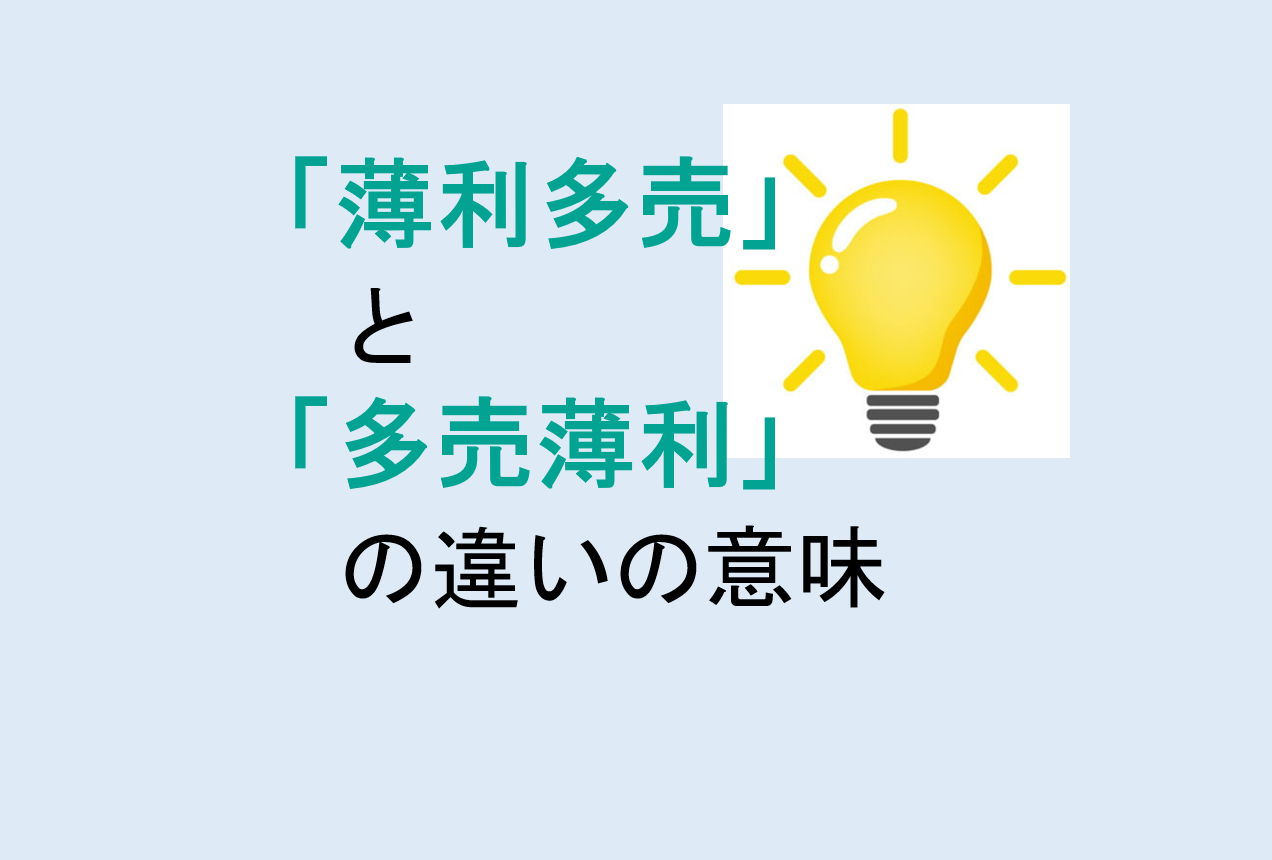ビジネスの世界では、薄利多売や多売薄利という言葉がよく使われます。
一見似ている表現ですが、実際には意味や使われ方が大きく異なります。
薄利多売は、意図的に利益を小さくして大量販売によって総利益を確保する戦略を指します。
一方、多売薄利は、戦略ではなく結果として「売れているのに儲からない」状態を表す言葉です。
どちらも売上や利益に深く関わる重要な概念であり、特に経営やマーケティングを考える上で押さえておくべきポイントです。
本記事では、それぞれの意味や使い方、そして薄利多売と多売薄利の違いを具体例を交えながら解説していきます。
薄利多売とは
薄利多売とは、1つあたりの利益を小さく設定し、その代わりに多くの商品を販売することで最終的に大きな利益を得る販売手法を指します。
経済学において「価格を下げると需要が増える」という基本原則があります。
薄利多売はこの原則を活かし、商品単価を下げて販売数を増やすことで総利益を確保する考え方です。
スーパーやディスカウントストア、ファストフード店などが典型的な例であり、大量販売が前提となる商売に適しています。
ただし、この手法は常に成功するわけではありません。
値下げによって販売数は伸びても、想定以上に販売が増えなければ十分な利益を確保できません。
また、価格競争に陥りやすく、利益率がさらに圧迫されるリスクもあります。
そのため、薄利多売は効果的な商品や業態を見極めて戦略的に取り入れる必要があるビジネスモデルだといえるでしょう。
薄利多売という言葉の使い方
薄利多売は、企業の販売戦略や経営方針を説明する際によく使われます。
特に小売業や飲食業など、大量販売を前提とした業界で頻繁に登場します。
薄利多売の使い方の例
-
ディスカウントストアは薄利多売の戦略で急成長した
-
高級ブランドには薄利多売の手法は向いていない
-
コンビニは薄利多売の典型的なビジネスモデルだ
多売薄利とは
多売薄利とは、たくさん売れているにもかかわらず、利益が少ない状態を指す言葉です。
薄利多売と違い、意図的な戦略ではなく、結果として「売上は伸びたのに利益は伴わない」状況を表します。
例えば、価格を下げすぎて利益率が極端に低くなった場合、販売数が増えても経費や人件費を差し引くとほとんど利益が残らないことがあります。
これが多売薄利です。
企業にとっては健全な状態とは言えず、経営を圧迫するリスクのあるマイナスな意味合いを持つ表現です。
典型的なケースとしては、過度な値下げ競争に巻き込まれた小売業や、広告費や人件費が膨らんで利益を食いつぶしている状況などが挙げられます。
つまり、**多売薄利は戦略ではなく「儲からないビジネスの落とし穴」**として認識すべき言葉です。
多売薄利という言葉の使い方
多売薄利は、企業の収益状況や経営上の失敗を指摘する場面で使われます。
売れているのに利益が出ないという矛盾を表すため、ネガティブな意味合いで使われるのが特徴です。
多売薄利の使い方の例
-
売上は伸びたが多売薄利で経営が苦しい
-
多売薄利に陥り、赤字が続いている
-
大ヒット商品が出たが利益は少ない多売薄利の状態だ
薄利多売と多売薄利の違いとは
薄利多売と多売薄利の違いは、「戦略か結果か」という点にあります。
まず、薄利多売は企業が意図的に選択する販売戦略です。
価格を下げて販売量を増やし、総利益を確保しようとする前向きなビジネスモデルであり、ディスカウントストアやチェーン展開をしている飲食業で広く採用されています。
一方、多売薄利は意図せず陥ってしまう経営状態です。
値下げ競争やコストの増大などにより「たくさん売れているのに利益が出ない」状況を表します。
つまり、薄利多売は能動的な戦略、多売薄利は望ましくない結果という違いがあります。
例えば、スーパーが戦略的に価格を下げて集客し、回転率を高めて利益を出すのは薄利多売です。
しかし、無理な値下げで利益率が極端に低く、売れても経費に吸収されてしまうのは多売薄利です。
両者は言葉の並びが似ているため混同されがちですが、その意味は正反対といってよいでしょう。
この違いを理解しておくことで、経済ニュースやビジネス書での用語の使い分けが明確になり、企業分析や経営戦略を考える際に大いに役立ちます。
まとめ
薄利多売と多売薄利の違いは、戦略か結果かという点にあります。
薄利多売は「小さな利益でも大量販売によって利益を確保する」前向きな販売戦略であり、多売薄利は「たくさん売れているのに利益が残らない」望ましくない経営状態を指します。
両者を正しく理解することで、ビジネス用語を的確に使い分けられるようになります。
さらに参考してください: