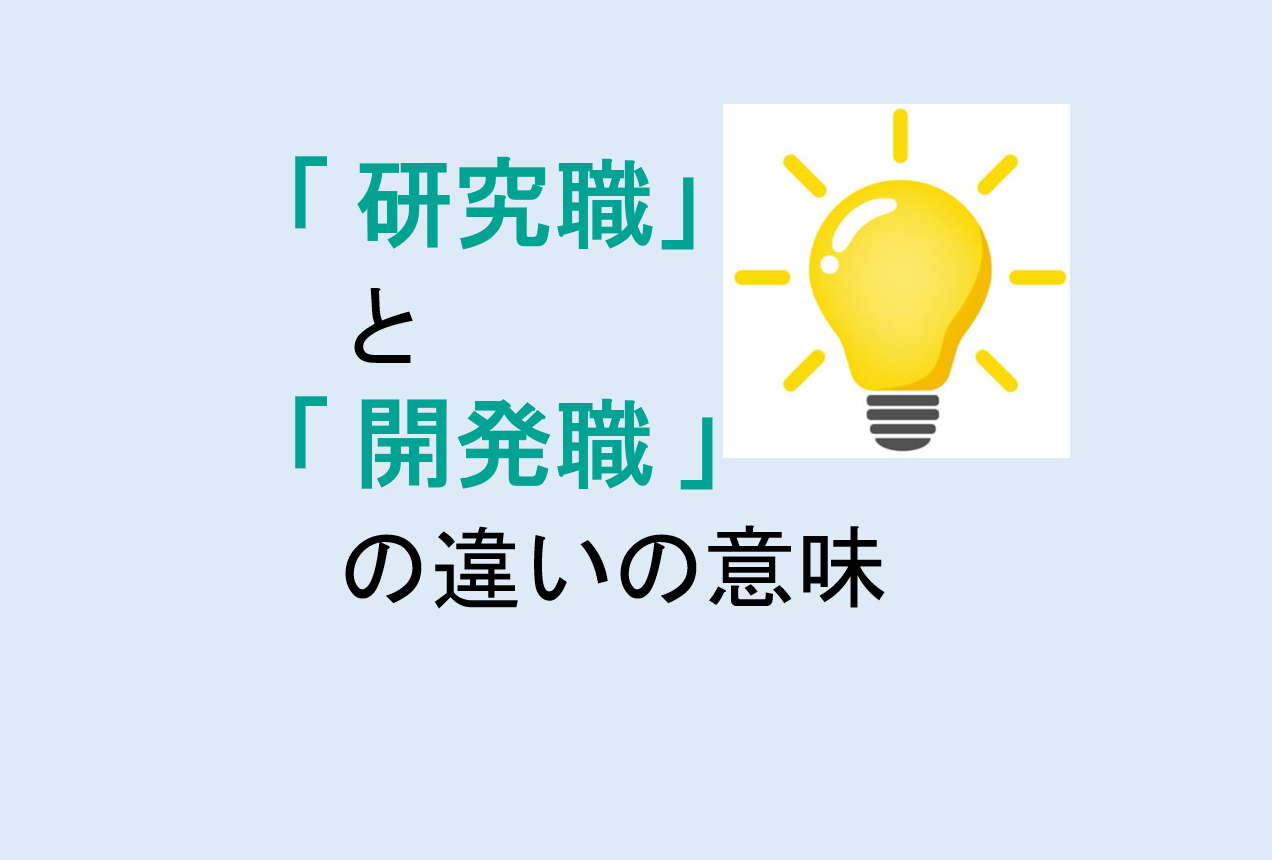就職活動やキャリア選択の場面でよく耳にする研究職と開発職。
どちらも理系の仕事として知られていますが、その内容には明確な違いがあります。
本記事では、研究職と開発職の違いを分かりやすく解説します。
それぞれの仕事内容、職場環境、求められるスキルの違いに触れながら、どのような人に向いているかも紹介します。
これから職業選択をする方や、理系の職種に興味がある方にとって、役立つ情報が満載です。
研究職とは
研究職とは、物事を科学的・体系的に調査し、新しい理論や事実を明らかにすることを職業とする人のことを指します。
主な仕事内容には、基礎研究や応用研究が含まれます。
基礎研究では、実用性を直接追求するのではなく、自然現象の解明や理論の構築を目的とします。
一方、応用研究は、特定の課題や目的をもとに、得られた知識や理論を活用して実用的な成果に繋げることを目指します。
研究職の勤務先には、大学・大学院、企業の研究開発部門、国や地方自治体の研究機関などがあります。
研究の成果は論文として発表されたり、新技術の基盤として実用化に繋がったりします。
また、研究職は高度な専門性が求められるため、大学院(特に修士・博士課程)を修了してから就職するのが一般的です。
研究職という言葉の使い方
研究職という言葉は、主に職業やキャリアに関する場面で使用されます。
採用試験、職業紹介、就職活動の志望動機などで使われることが多く、一般的な日常会話ではあまり登場しません。
例:研究職の使い方
-
将来は研究職に就いて新薬の開発に貢献したいです。
-
大学院修了後、化学メーカーの研究職に内定しました。
-
研究職を目指して、論文執筆にも力を入れています。
開発職とは
開発職とは、新しい技術や製品を実用化するための開発を担当する職業です。
市場ニーズを把握し、それに応じたアイデアを企画・設計・試作・製造まで導く役割を担います。
開発の対象は多岐にわたり、家電、食品、化粧品、自動車、ソフトウェアなど、私たちの生活に密接に関わる製品が中心です。
具体的には、消費者の声を調査し、新しい機能やデザインを考案し、製品として形にしていきます。
製品完成後も、その販促戦略や改善案を検討する工程に関わることもあります。
開発職の多くは民間企業に勤務しており、チーム単位でのプロジェクトが中心となります。
そのため、チームワークやコミュニケーション能力も重要視されます。
大学卒業程度の学歴が求められ、特別な資格が必要になることは少ないですが、専門知識や実務経験があると採用に有利になる場合もあります。
開発職という言葉の使い方
開発職も、主に職業や業務内容を説明する場面で使われます。
企業の採用情報、職務経歴書、キャリア相談などでよく使われますが、日常会話で使われる頻度は少なめです。
例:開発職の使い方
-
私は食品メーカーで開発職として働いています。
-
将来は化粧品の開発職に就いて、オリジナル商品を手がけたいです。
-
開発職に求められるのは、柔軟な発想力と実行力です。
研究職と開発職の違いとは
研究職と開発職の違いは、主に業務の目的と内容にあります。
研究職は、理論や真理の追求を目的とし、長期的な視点で未知の分野に挑む仕事です。
基礎研究や応用研究を通じて、新しい知識や原理を発見し、それを論文や学術的成果としてまとめることが主な業務です。
多くの場合、大学院で専門知識を深め、研究成果を世に出すことが求められます。
一方、開発職は、既存の理論や技術をベースに、製品やサービスとして市場に届けることが目的です。
顧客ニーズを反映し、企画から試作、量産化、販売戦略までを一貫して担当します。
実用化・商用化に重きを置いており、より短期的な成果が求められるケースが多くなります。
また、働く場所にも違いがあります。
研究職は大学や国の研究機関、または企業の研究部門が多いのに対し、開発職は主に民間企業の製品開発部門で活躍します。
学歴の面では、研究職には大学院卒(修士・博士)が多く求められるのに対し、開発職では大学卒でも応募が可能なことが一般的です。
さらに、仕事の進め方にも差があります。
研究職は個人の探求心が重視される傾向にありますが、開発職はチームでの連携が重要です。
両者は、「研究開発職」として一体化されることもありますが、求められる役割やスキルセットには明確な違いがあります。
まとめ
研究職と開発職の違いは、仕事の目的や進め方、職場環境などに明確に表れます。
研究職は新しい知識の探求や理論の構築を担い、開発職はその知識を活かして具体的な製品や技術を生み出します。
どちらも社会に貢献する重要な役割を持ちますが、求められるスキルや資質は異なります。
自身の興味や適性、キャリアプランに合わせて、適切な職業選択をすることが大切です。
さらに参考してください: