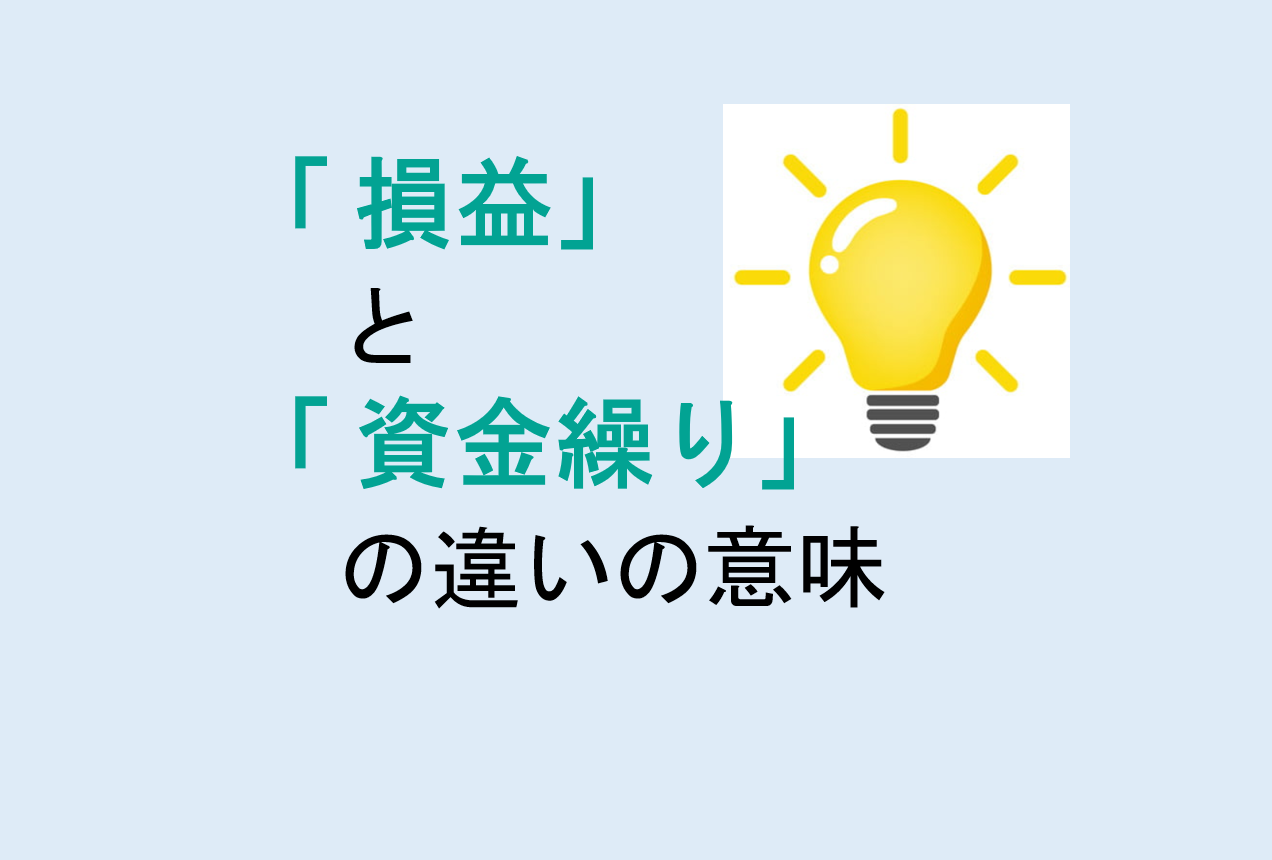企業経営やビジネスの現場で頻繁に登場する言葉に、損益と資金繰りがあります。
一見似たように聞こえますが、その意味や役割は大きく異なります。
損益は会計上の利益や損失を示すものであり、資金繰りは現金の流れを把握し、必要に応じて資金を確保する行為を指します。
本記事では、両者の意味や使い方、そして具体的な違いについて分かりやすく解説します。
企業経営に携わる方だけでなく、日常生活でお金を管理する上でも役立つ知識となるでしょう。
損益とは
損益(そんえき)とは、「損失」と「利益」を合わせた言葉で、会計上の収益と費用の差額を表します。
企業の経営成績を示す重要な指標であり、売上から費用を差し引いた結果、黒字(利益)か赤字(損失)かを判断する基盤となります。
会計では、取引が現金の動きと同時に行われるとは限りません。
例えば、売上が立っても入金は後日になることがあります。
そのため、「売掛金」「買掛金」「未払費用」といった科目を用いて、発生した時点で損失や利益を記録し、正確な経営状況を把握できるようにしています。
ビジネスの現場では、損益計算書が代表的な資料として使われます。
これは売上高、売上原価、経費、営業利益などを一覧にしたもので、企業の収益力を評価するために欠かせません。
また、損益は単独ではなく「貸借対照表」と併せて分析することで、より正確な経営判断に役立ちます。
損益という言葉の使い方
損益は主に会計や経営に関する文脈で使われます。
「損益が発生する」「損益を計上する」といった表現で、利益や損失に関わる数値の動きを示す際に用いられます。
例:損益の使い方
-
この商品の売れ行き次第で会社の損益に大きな影響が出る。
-
新しい取引先との契約では損益をしっかり考慮する必要がある。
-
税務署は急激な損益の変動を注意深くチェックしている。
資金繰りとは
資金繰り(しきんぐり)とは、会社や個人のお金の収入と支出を計算し、資金不足が起こらないように調整することを意味します。
企業においては、売上や借入金などの入金と、人件費や仕入代金などの支出を管理し、資金ショートを防ぐことが最大の目的です。
例えば、売上が伸びていても入金が遅れれば、手元の現金が不足して支払いに困るケースがあります。
このような場合に銀行融資や資産売却などを行って資金を確保するのが資金繰りです。
また、会計用語としてだけでなく、日常生活でも「今月は生活費の資金繰りが大変だ」といった形で使われることがあります。
つまり、必要な資金を確保するための具体的な工夫や調整全般を指す言葉です。
資金繰りという言葉の使い方
資金繰りは、企業経営における現金管理から、個人の生活費調整まで幅広く使われます。
「資金繰りを行う」「資金繰りに失敗する」といった表現が代表的です。
例:資金繰りの使い方
-
A社は資金繰りに失敗し、支払いが滞ってしまった。
-
この資金繰り表によると、来月の現金残高が不足する可能性がある。
-
生活費が足りず、今月は友人から借金して資金繰りをした。
損益と資金繰りの違いとは
損益と資金繰りの違いは、「会計上の収益・費用を扱うか、実際の現金の流れを扱うか」という点にあります。
損益は発生主義会計に基づいて記録されます。
取引が実際に現金で動いたかどうかに関わらず、その取引が発生した時点で収益や費用を計上します。
したがって、企業の経営成績を正確に表すことができますが、現金残高とは一致しない場合があります。
一方、資金繰りは実際のキャッシュフローに焦点を当てます。
どれだけお金が入ってきて、どれだけ出ていくのかを管理することで、資金不足を防ぎます。
企業にとっては、黒字であっても資金がショートすれば倒産につながる可能性があるため、資金繰りの管理は損益以上に重要とされることもあります。
簡単にまとめると、損益は「利益や損失の計算」、資金繰りは「現金の流れの管理」と言えるでしょう。
どちらも企業経営に欠かせない概念であり、両者を正しく理解して併用することで、健全な経営判断が可能になります。
まとめ
損益は企業の収益と費用を計上し、経営成績を把握するための指標です。
一方で、資金繰りは実際の現金の流れを管理し、資金不足を防ぐための調整を指します。
つまり、損益が「利益・損失の計算」、資金繰りが「現金の確保と調整」と覚えると分かりやすいでしょう。両者を正しく理解しバランスよく管理することが、企業の安定経営につながります。
さらに参考してください: