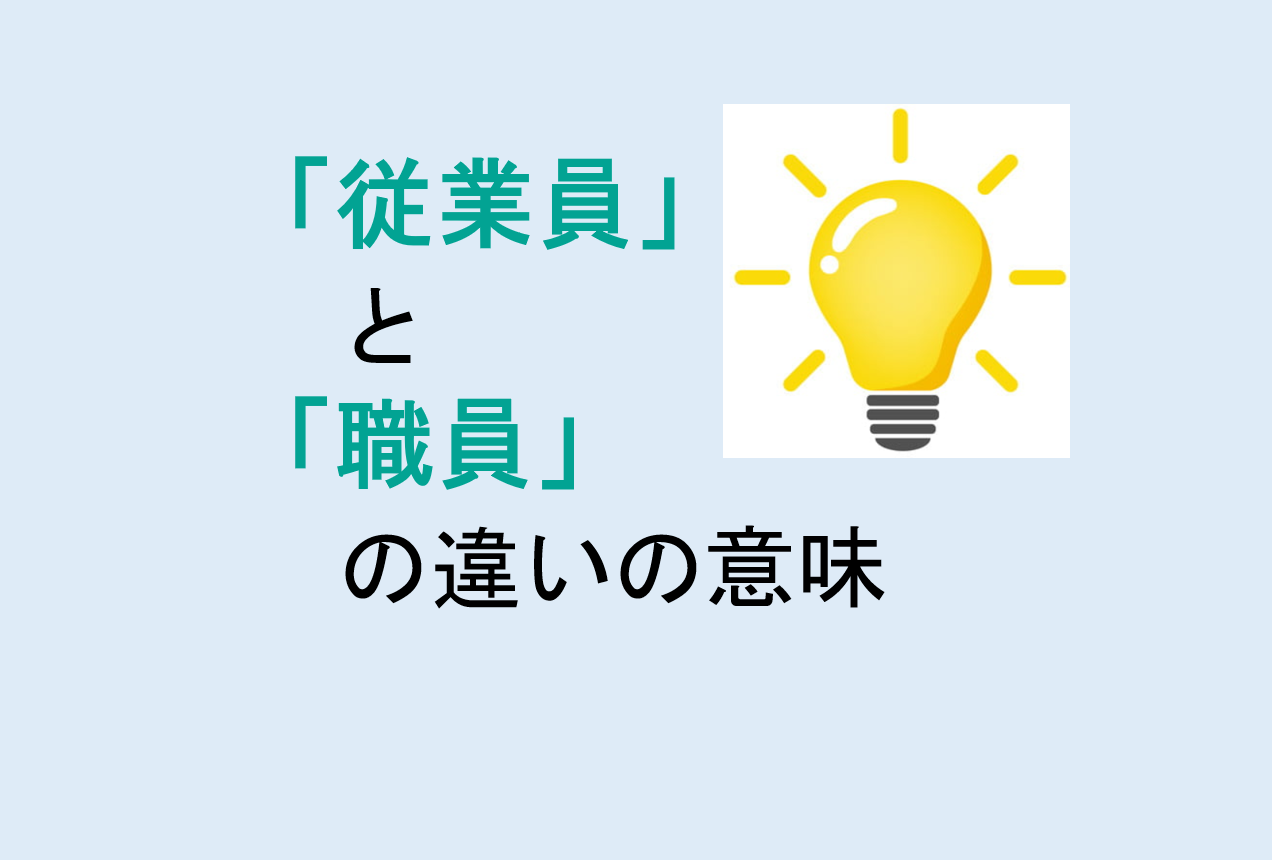会社や官公庁などで働く人を表す言葉として、よく使われるのが従業員と職員です。
日常会話やニュース記事でも目にする機会が多い言葉ですが、その意味や使い方には違いがあります。
ときには同じ意味で使われることもありますが、厳密には対象となる人の範囲や使われる場面が異なります。この記事では、従業員と職員の定義や使い方の違いをわかりやすく解説し、例文を交えて理解を深めていきます。
仕事や学習で正しく使い分けられるよう、ぜひ参考にしてください。
従業員とは
従業員とは、企業や団体の指揮命令下で働くすべての人を指す言葉です。
正社員だけでなく、契約社員や派遣社員、パートやアルバイトまで、雇用形態や役職を問わず広く含まれます。
場合によっては会社役員も含むことがありますが、経営に携わる立場は従業員から外されることもあります。
つまり、会社や組織の業務に従事している人は基本的に全員「従業員」と呼ばれます。
法律用語やビジネス文書でも使われることが多く、雇用関係にある人を包括的に示す便利な言葉です。
企業の規模を問わず、働く人をまとめて表現する際によく用いられます。
この言葉の背景には、労働者を一律に指し示すニュートラルな意味合いがあり、組織における立場や職務内容を限定しない特徴があります。
そのため、企業が従業員向けの福利厚生や研修を行う際などにも広く活用されます。
従業員という言葉の使い方
従業員は、企業や団体で働く人をまとめて指す際に使われます。
個人を指すよりも集団としての「働き手」を表すニュアンスが強く、会社の規模や活動を示す際に便利な表現です。
例:従業員の使い方
-
当社の従業員は全国で1万人を超えています。
-
従業員に向けた安全研修を毎月実施している。
-
不況の影響で多くの従業員が配置転換となった。
職員とは
職員とは、職場で業務に従事している人を意味します。
特に官公庁、学校、研究機関、病院といった公共性の高い組織でよく用いられる言葉です。
法律的には、雇用関係に基づき働いている人を指し、経営者や役員などは含まれません。
民間企業で働く人を指すこともできますが、一般的には「会社員」というよりも「役所の職員」「学校の職員」といった使い方が自然です。
個人事業主やフリーランスには使えない点も特徴的です。
職員という言葉には、公的な組織に属し、一定の職務を遂行する人というイメージがあります。
そのため、堅い場面や公的文書で多用され、社会的な役割や責任を示す表現として適しています。
職員という言葉の使い方
職員は、公的機関や教育機関で働く人を表す場面で使われることが多いです。
会社で使うことも可能ですが、一般的にはあまりなじみのない用法です。
例:職員の使い方
-
市役所の職員として地域住民の相談に応じる。
-
大学の職員が入学手続きをサポートする。
-
空港の職員に案内を受けて手続きを進めた。
従業員と職員の違いとは
従業員と職員の最大の違いは、「対象範囲」と「使われる場面」です。
まず、従業員は企業や団体に雇われて働くすべての人を指し、正社員だけでなくアルバイトや派遣社員なども含まれます。
雇用関係を広く示すため、企業活動全体や労務管理の文脈でよく使われます。
一方、職員は職場で業務に従事する人を指しますが、特に官公庁や学校、病院などの公的組織で働く人を指すケースが多いです。
また、法律上は雇用契約を結んでいる労働者を意味し、経営者や役員は含まれません。
例えば、同じ会社で働く人でも「従業員数は300名」と表現するのに対し、公的機関では「市役所の職員は500名」といった使い方をします。
両者には重なる部分もありますが、従業員は幅広く使える一般的な言葉、職員は特定の職場や役割を強調する言葉という違いがあります。
まとめ
従業員と職員は、どちらも「働く人」を指す言葉ですが、その使われ方や対象範囲には違いがあります。
従業員は企業で働くすべての人を包括的に表す一方、職員は主に官公庁や学校などで働く人を指す傾向があります。
両者の違いを理解して使い分けることで、より正確な表現が可能になります。
仕事や日常会話で混同しやすい言葉だからこそ、正しく使いこなすことが大切です。
さらに参考してください: